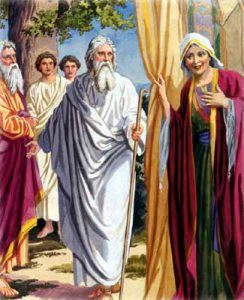音声:信仰の列伝(18) 天の故郷にあこがれる信仰(1) へブル人への手紙11章13節
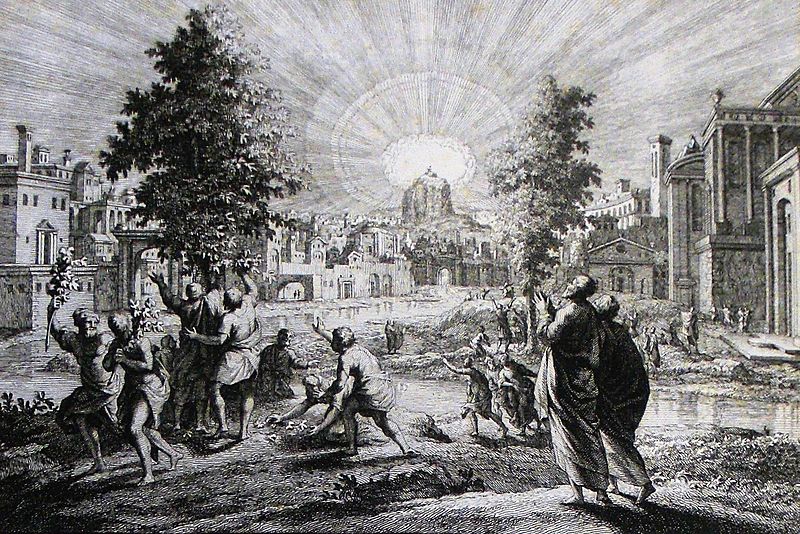
オランダの地図および彫刻画の製作者であったPieter Mortier (1661–1711)により作成されたMortier’s Bibleの挿絵「The tree of life(いのちの木)」。(Phillip Medhurst Collection。Wikimedia commons より)
2016年11月27日(日)午前10時半
礼拝メッセージ 眞部 明牧師
へブル人への手紙11章13節
11:13 これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。
はじめの祈り
「信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。」
恵みの深い天のお父様、こうして恵みの中で私たちをお守り下さり、今年もはや11カ月をお守りくださり、様々な課題、山坂を乗り越えて、今日の日まで守られ、感謝をいたします。
私たちもまた、地上では旅人であり、寄留者でありますけれども、遥かに天の故郷を見て喜び迎える信仰をお与えくださっていることを、感謝いたします。
今日もイエス様の恵みを深く経験できますように、イエス様の助けをお与えください。
尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日は信仰の列伝の18回目、「天の故郷をあこがれる信仰」の1回目として、お話をさせていただきます。
今日は、13節だけをお読みしましたけれども、13節~16節は、これまで取り上げてきた信仰者の信仰生活の目的が何であるか、をはっきりと教えています。目的を見失うと、私たちは放浪者になってしまいます。
モーセの時代に、イスラエルの民がエジプトから脱出して、神の約束の地を目指していた時は、目的地がありましたから、放浪者ではありませんでした。しかし、カデシュ・バルネヤで不信仰になった時、神様は一緒に行かない、と仰いました。それから先は、40数年間イスラエルの民は、同じシナイの荒野をぐるぐる回って、目的地のない放浪の旅を続けることになったのです。
私たちがもし、天の故郷を目指すことを忘れてしまって、この地上での喜びだけを体験しようとするなら、目的地を失って放浪の旅になってしまいます。目先の楽しみや快楽を求めるようになってしまいます。ですからこの話は重要であることが分かります。
13節のはじめに、「これらの人々」とあります。これは4節のアベルからの話の続きと考えれば、いろいろな聖徒のことが言われていると思いますけれども、15節、16節からは、故郷のことが話されていますから、アブラハムとサラのことを中心に話されていると思います。
彼らはなぜ、あえて数々の困難を乗り越えて、忍耐して、信仰の旅を続けたのでしょうか。
決して楽な生活ではありません。もし彼らの信仰が、知識による理解であるものなら、また律法学者のような議論で終わってしまうものなら、口ではいくら熱心に話をしても、自分からは決してカルデヤのウルから出ることもなく、また、十年ほど住んだパダン・アラムを出て、旅をすることもなかったでしょう。人の熱心から出る議論は、なんの信仰の行いももたらさないからです。
自分では何もしないけれども、議論好きな人、そういう律法学者をイエス様は厳しく叱責しました。言葉では厳しく他人に教えているけれども、自分では何もしない。良きサマリヤ人の話の中の祭司やレビ人と同じであります。行き倒れている旅人を助けることもなく、通りすぎて行ってしまう。理論は正しいかもしれない、儀式も正しいかもしれない。しかし、信仰の働きがない。
ですから、アブラハムとサラの信仰の旅は、明確な神のご命令を聞いて受け入れた、という事実に基づいていたからです。
神のご命令がはっきりしないで、自分の思いこみぐらいで従っていても、困難の多い、長い信仰の旅を到底続けることはできません。信仰を持って数日、数カ月、数年喜んでいるかもしれませんが、それが生涯続く、ということはあり得ないことです。
神の御命令のみことばに基づいてこそ、私たちは信仰を全うすることができます。
アブラハムとサラは、天のふるさとを憧れていました。
このことは非常に驚きました。なぜかというと、彼らは旧約の人なのに、はっきりと復活の信仰を持っていたからです。
私たちはすでにイエス様の復活を経験していますし、復活の信仰を信じていますから、素晴らしい恵みを受けているわけですけれども、まだイエス様の復活が将来のことである、そういう時代に、アブラハムとサラは復活の信仰を持っていた。しかも、今日のクリスチャンより、熱心に求めています。
彼らは、この地上の出来事、生活、苦難や繁栄を知っていたと思いますけれども、彼らはこの地上を去って、天の故郷の生活の方が、ずっと栄光に満ちている、ということを悟っていました。旧約の人だから、信仰が劣っているというのは、間違いですね。
ローマ8章18節をお読みしましょう。今と将来のことが対比されています。
ローマ8:18 今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。
いつもお話ししますけれども、「考えます」とか「思います」とかいうのは、「計算します」ということですね。いろいろと体験したけれども、こう決定しました、ということですね。確かに今、イエス様を信じて苦しみを経験しているけれども、将来私たちが受ける栄光に比べると、取るに足らないものと計算します、そう決済しました、ということですね。そういう信仰を表わしているんです。
ローマ8章24節、25節も読んでみたいと思います。
ロ-マ 8:24 私たちは、この望みによって救われているのです。目に見える望みは、望みではありません。だれでも目で見ていることを、どうしてさらに望むでしょう。
8:25 もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは、忍耐をもって熱心に待ちます。
目に見える望みとは、もうすでに掴んでいるもののことですね。実現化している、現実化していることです。つまり地上のことですね。これはもう望みではない。
目に見えていないこと、私たちにとっては霊の世界のこと、経験はしているけど目で見ていない、実際に手で掴んでいない、天の故郷のことであります。それなら、私たちは熱心に待ちます、と言っています。
第二コリント4章14節から18節まで、少し長いですけれども、読んでみたいと思います。目に見えていないものが何であるか分かります。
Ⅱコリ4:14 それは、主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスとともによみがえらせ、あなたがたといっしょに御前に立たせてくださることを知っているからです。
4:15 すべてのことはあなたがたのためであり、それは、恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためです。
4:16 ですから、私たちは勇気を失いません。たとい私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。
4:17 今の時の軽い患難は、私たちのうちに働いて、測り知れない、重い永遠の栄光をもたらすからです。
4:18 私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。
ここには、見えるものと見えないものとの話がありましたけれども、その代表的なことは、主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスとともによみがえらせる。
とても大事なことですね。
イエスとともに、と言うのは、一緒に、と書いてありますけれども、イエス様を持っている人、私のうちに目に見えていないイエス様を宿している者は、よみがえられる。
今の時の軽い患難は、私たちのうちに働いて、イエス様の復活のいのちがうちに働くことによって、測り知れない永遠の栄光をもたらす、復活させてくださる。ですから、見えないものを求めると言っているわけです。
私たちは日頃、この世の仕事に追いかけ回されています。そのため、永遠の栄光を思い見ることを見失ってしまいがちです。ですから、天の故郷を恋い慕う心を見失なわないようにしなければいけません。
パウロは「いつまでも残るものは信仰と希望と神の愛だ」と言いました。
主を愛して、隣り人を愛して、永遠の御国の栄光を獲得する。それは決して失われることのない、永遠の輝きです。私たちは、普段に、永遠の輝きを持って、輝いて生活することができるわけです。
パウロはピリピの忠実なクリスチャンたちに、次のように忠告しています。ちょっと何か所か、ピリピの手紙を読んでみたいと思います。
ピリピ2章3節 「何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自分よりもすぐれた者と思いなさい。」
3章9節も読んでみましょう。
「キリストの中にある者と認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち、信仰に基づいて、神から与えられる義を持つことができる、という望みがあるからです。」
注意していただきたい言葉があります。パウロは信仰の基本的な本質を、律法を守る自分の義ではない、と言いました。クリスチャンが気を付けなくてはならないことがあります。儀式を守ることによって、自分の真面目さや正しさによって、満たされているわけではない。
最初はイエス様の十字架の信仰から始まったのに、いつの間にか自分は周りの人々より正しいというような、心の中の誇りが土台になってしまいやすいです。
自分の正しさ、熱心さ、真面目さ、他人よりすぐれていること、そういうことによって義が保たれているのではありません。
キリストを信じる信仰、神様から与えられた義を持つこと、これが大事ですね。パウロが求めたのは、キリストを信じる信仰ですけれども、自分を誇らせる自己義ではありません。信仰によって神から与えられる神の義です。なぜこれが大事かというと、この神の義が、復活の力を与えるからです。
もし皆さんが、自分の正しさや真面目さ、熱心さ、人より優れているところを誇りとしているならば、あなたの復活をさせません。パウロはそう言っているんですね。私たちを復活させる義は、キリストを信じる義でなければならない。神様が与えて下さる義でなくてはならない。
ピリピの3章10節~11節を読んでみたいと思います。
ピリピ3:10 私は、キリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみにあずかることも知って、キリストの死と同じ状態になり、 3:11 どうにかして、死者の中からの復活に達したいのです。
パウロも、アブラハムも、サラも、同じですね。求めている所は、天の故郷であり、死者からの復活に達することでした。パウロの唯一の望みは、キリストの復活にあずかって、復活の栄冠を獲得することであります。信仰者は、どこを目的にしているかが非常に大事なことですね。
ピリピの3章14節を読んでみたいと思います。
ピリピ3:14 キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目ざして一心に走っているのです。
マラソンランナーのようですね。最後のゴールを獲得するためです。途中で倒れてしまわないように。旧約の聖徒も、新約の聖徒も、概念だけではなくて、実際の天の御国を目指して走っているランナーです。私たちはこのことを忘れてはなりません。
ピリピ3章18節~19節を読んで見ましょう。
ピリピ 3:18 というのは、私はしばしばあなたがたに言って来たし、今も涙をもって言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。
3:19 彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。
パウロの時代から、信仰の目的を間違えている人がいた、ということですね。一生懸命なのだけれども、中身を見ると自分の欲と滅びの道を歩いてしまっている、ということですね。
ピリピ2章21節も読んでみましょう。
ピリピ2:21 だれもみな自分自身のことを求めるだけで、キリスト・イエスのことを求めてはいません。
さらに手厳しいことを言われています。結局求めているのは自分自身のことだけだ、と言っています。キリスト・イエスのことを求めていません。パウロはこれらのことが未信者の世界だけではなくて、教会の中に生じていることを懸念しています。
パウロはテモテに次のように忠告しました。そこも読んでみたいと思います。
第二テモテ4章2節から5節
Ⅱテモテ 4:2 みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また勧めなさい。
4:3 というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分につごうの良いことを言ってもらうために、気ままな願いをもって、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、 4:4 真理から耳をそむけ、空想話にそれて行くような時代になるからです。
4:5 しかし、あなたは、どのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。
そしてパウロは、最後に義の栄冠を確信したんですね。第二テモテの4章6節から8節も読んでみたいと思います。
Ⅱテモテ 4:6 私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。
4:7 私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。
4:8 今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、だれにでも授けてくださるのです。
パウロは明らかに、アブラハムやサラと同じように、天の故郷を求めていたことが分かります。
私の経験ですけれども、昨年は吉田きみこさんを天にお送りしました。
穴井善三君や渡辺暢子姉妹や、そのほかの方々も天にお送りしてきました。
先日も道を歩いていましたら、年配のご婦人が立ち話で、「みんなが行くところだから」という話が聞こえてきました。話を続けて聞いていると「死」のことを言っているようでありました。
主イエス様の再臨がいつあってもおかしくない日が、昨今、続いていることを、皆さんもお気付きのことと思います。全世界が終末の時を迎えようとしています。避けられません。天の御国は、もう扉の向こう側まで近づいているんです。
私たちは、この世のことに心を奪われて、神の国が来ることを気付いていなかったら危険な目にあってしまいます。ですからもっと声を高くして、このことをお伝えする必要があるでしょう。
マタイ16章26章から28節を読んでみたいと思います。
マタイ 16:26 人は、たとい全世界を手に入れても、まことのいのちを損じたら、何の得がありましょう。そのいのちを買い戻すのには、人はいったい何を差し出せばよいでしょう。 16:27 人の子は父の栄光を帯びて、御使いたちとともに、やがて来ようとしているのです。その時には、おのおのその行いに応じて報いをします。
16:28 まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。」
私の心がこの世のことに捕らわれてしまうなら、天の御国が私の心から締め出されてしまいます。イエス様を信じていると言っても、この世的なものが入ってくるからですね。私たちの生活は、いつもこのようなものに取り囲まれて、思い煩いに陥りやすいわけです。結局、父なる神様を心で仰がないで行ってしまう。パウロが言ったように、この地上の欲のために、主なる神様を利用するだけになってしまいます。
ヘブルの11章13節では、先ほども読みましたが、「これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでした」
このことはアブラハムとサラの生涯の間に、キリストの十字架や復活や再臨が実現していなかったことを示しています。彼らは素晴らしい信仰者でありましたけれども、私たちと同じように、キリストの贖いと復活と再臨を通して、その信仰の完成を全うすることができます。報いを受けるまで待っているわけですね。ですから、天の故郷は、まだ未来のものです。しかしその約束は継続しています。
「信仰の人々として死にました」とは、パウロが第二テモテ4章7節で言った「私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました」と同じです。義の栄冠を受けるのための、信仰が完成したということです。
ヨハネの黙示録2章10節をご一緒に読んでみたいと思います。
黙2:10 あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ。悪魔はあなたがたをためすために、あなたがたのうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなたがたは十日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば、わたしはあなたにいのちの冠を与えよう。
ある時、年配のご婦人に私はこのみことばを書きました。
「死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば、わたしはあなたにいのちの冠を与えよう。」
ちょっとびっくりするようなことを手紙に書いたわけですけれども、返事が来ました。
「このことによって、信仰がはっきりしました。」と言いました。
私はその時、神のみことばは素晴らしいな、と思いましたね。人の心にいのちを与えるわけですから。神様は御業をおこなって、一瞬の内にその人の魂をいのちで満たしてしまわれます。素晴らしいことが起きたな、と思いました。
彼らは見ずに信じて、信仰によって天の故郷を愛するようになったわけです。
アブラハムやサラはキリストの再臨によって、その信仰が現実化するわけですけれども、キリストの再臨によって一斉に、御国の完成が顕在化します。その時まで待たなければならない。
詩篇116篇15節に「主の聖徒たちの死は、主の目に尊い」と、あります。なぜ尊いのか。詩篇16篇10節から11節で、ダビデはこう言いました。
詩16:10 まことに、あなたは、私のたましいをよみに捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。
16:11 あなたは私に、いのちの道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には、楽しみがとこしえにあります。
私たちの本当の喜びや楽しみは、どこにあるんでしょうか。
もちろん地上で楽しい事や、嬉しい事がたくさん起きるでしょう。しかしやがてそれは消えてしまいます。最終的な喜びは、神の御前にある喜びであります。このことを、旧約のダビデが経験していたんですね。聖徒の死は、墓の穴を見せないと仰いました。それで終わりではない、ということです。
イエス様は十字架にかかられてから、墓に入れられました。よみにまで下られた、と書いてあります。それは私たちのために必要だから経験したことですけれども、しかし、そこで終わっていません。「お見せにはなりません」というのは「見せない」ということではなくて、「それに縛られない、支配されない、捕らわれない」ということです。そこを突き破って、いのちに甦られたわけです。これはことばで言い表わすことができない経験ですね。お互いが、信仰によって神様と交わりの中で、経験して頂きたいと思います。
ヨハネ11章25節、26節を読んでみましょう。ここも人間の理性で考えて分かるものではありません。
ヨハネ11:25 イエスは言われた。「わたしは、よみがえりです。いのちです。わたしを信じる者は、死んでも生きるのです。
11:26 また、生きていてわたしを信じる者は、決して死ぬことがありません。このことを信じますか。」
これはベタニヤのマリヤとマルタに言われていることばの一つです。ラザロが亡くなった時に言いました。マリヤやマルタは、理性的に判断して、「終わりの日に甦ります」と、その信仰は間違っていなかった。しかし、イエス様が仰ったことはまた、別のことでありました。
死んでいない、死んでも生きている、決して死ぬことがない。ですから、これは、人間の知性では理解できないことであります。
信仰は「死」を超えて、天の故郷を味わわせてくださる。
いくらこの世の楽しみをさせてくれても、天の故郷を味わわせてくれる信仰がなければ、そういう信仰は、信じるに値しない。サタンのように、地上の繁栄だけを与えてくれる信仰は、信じるに値しない。
マタイの8章11節でイエス様は、「ただ、おことばをください」と言ったローマの百人隊長の信仰をお褒めになったあとで、こう仰いました。
マタイ8:11 あなたがたに言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国で、アブラハム、イサク、ヤコブといっしょに食卓に着きます。
これらは皆、もう「死」を乗り越えている人達ですね。天の故郷での話をしておられます。イエス様のお話は、もう地上を超えているものでありますから、地上のものだけを求めている人には、絶対に分からない奥義をお話になっておられます。
ですから私たちも天の故郷にあこがれを持って、この経験をすることができるみことばの信仰を、持たせていただきたいと思います。
ヘブル11章 13節「これらの人々はみな、信仰の人々として死にました」とは、ただ信仰者としてその生涯を閉じた、というだけではありません。「死」の向こうにある、神の約束の実現の天の故郷をつかんで、地上を去った、ということであります。
言葉で表すことはできません。確信を持って死んだ、という以上のことですね。
どういうふうに表現したらいいか分かりませんけれども、「この世」と「死の向こうにある神の約束の地」と、カーテン一つで隔てられているとすれば、カーテン越しに手を伸ばして、天の故郷をつかんで、地上を去ったと言うことができるでしょう。死のすぐ向こうに、神の約束の成就があるということをつかんで死んだということであります。信仰はそれができる。
彼らは、天の故郷は、死のすぐ向こうに、手を伸ばせばつかむことができる、すぐに得られる、現実の事実として、信じて死についたわけです。私の信仰も、今、天の故郷まで、現実のものとして信じる信仰になっていなければなりません。
見えているところは、地上のことかも知れませんが、先ほど読みましたように、見えているところではなくて、見えないものにこそ、栄光があります。
13節で、「約束のものを手に入れることはありませんでした」とあるのは、先ほどお話ししましたように、旧約の聖徒たちは、まだイエス・キリストを見ていなかったからです。神の約束は、イエス・キリストによってすべて成就するんですね。
第二コリントの1章20節を読んでみましょう。全ては、キリストが鍵になっていることが分かります。
Ⅱコリ1:20 神の約束はことごとく、この方において「しかり」となりました。それで私たちは、この方によって「アーメン」と言い、神に栄光を帰するのです。
旧約の聖徒たちは、私たちと同じように、キリストのみわざ、十字架と復活と再臨とが完成するまで待たなければなりません。私たちは旧約聖書を読んでたくさん教えられますけれども、彼らはまだ受けるべきものをすべて受けているわけではない。私たちと一緒に受けるわけですね。真に申し訳ないことですけれども。これは、イエス様のお計らいであります。
私たちは、すでにイエス・キリストの地上での贖(あがな)いのみわざは完成しています。十字架、復活、ご昇天、聖霊の降臨、内住のみわざを経験しています。また、霊的な神の約束は経験させていただいております。たましいの生まれ変わりや、聖霊の満たしや、きよめの経験も受けております。
しかし、永遠の新しい天、新しい地での生活の実現は、もう一つのキリストのみわざ、すなわちキリストの再臨の日まで待たなければなりません。聖書はそのことを教えています。第一テサロニケの手紙4章14節から17節を読んでみましょう。
Ⅰテサ4:14 私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのように、イエスにあって眠った人々をイエスといっしょに連れて来られるはずです。
4:15 私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが、死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。
4:16 主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、
4:17 次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして、私たちは、いつまでも主とともにいることになります。
こういう話を未信者の家族にお話してご覧なさい。「あなた、そんなことを信じているの?」と言われてしまうでしょう。しかし、聖書はそう言っているんですね。
自分の知恵で考えれば、そういうことはあり得ないだろうと思うかもしれません。
自分の判断で、ことが起きているんじゃないんです。これまでの過去の歴史において、人間が想定したことだけが起きているのではありません。地震が起きるんだって、予測できないではありませんか。
聖書が示していることは、全部預言が実現しています。ですから私たちは、信じるか、信じないか、でありますね。聖書で、イエス様は「信じない者にならないで、信じる者になりなさい。」と教えました。
第一テサロニケの5章23節も読んでみましょう。
Ⅰテサ5:23 平和の神ご自身が、あなたがたを全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨のとき、責められるところのないように、あなたがたの霊、たましい、からだが完全に守られますように。
主イエス様が再臨されるに先立って、今眠っている聖徒たち、先に天に送られている人達が、長く生きたか短く生きたかは問題ではありません。100歳まで生きた方も、あと10日で100歳になる方もいらっしゃいますし、穴井善三君は18歳で生涯を閉じましたが、それは問題ではない。
非情な病で死を遂げたかどうかも問題ではなく、ただ一つの点で重要な一致があります。それは、これらの人々が主イエスを信じて、心に宿して、天の故郷を待ち望んでいて死をとげた、ということであります。
私の心に留まっている一つのことば、穴井善三君はこう言いました。
私がお見舞いに行った時に、「私は死んでも、イエス様のところに行くから心配ない」と言いました。私は、この子は素晴らしいことを経験しているなあ、と思いました。
彼は確かに、心の中に天の故郷を待ち望んでいたことは明らかであります。ですから、聖徒の死は主のみ前で尊いのです。そのたましいのうちに天の故郷を持っているからであります。
彼らの信仰の記録は、証しですね。その証しも尊いものです。彼らは信仰によって生き抜いた義人であります。
信仰が、内なるキリストが彼らのいのちとなり、慰めとなり、動機となり力となっています。そうでなければ、若い18歳の青年が「死」を恐れないはずがありません。
彼らは生きている間に与えられた永遠のいのちと、霊的な恵みと、神の愛と、平安を持って、天の御国に入っていきました。
地上にある時は、病や様々な課題のために、苦難の中で祈っています。霊の歌を歌っています。
しかし、その祈りも歌も歌い終わって、これからは、勝利の賛美を、ヨハネ黙示録の聖徒たちのようにハレルヤと歌うのです。
間もなくクリスマスになって、メサイヤやハレルヤコーラスが歌われると思いますけれども、できれば歌だけではなくて、お一人お一人の心の中に、たましいの中に、神の国を心に持ってハレルヤを歌ってほしいと思います。
讃美の歌声が素晴らしいのではなくて、聖徒の死が尊いのは、その人のたましいのうちに神の国があることですね。神の国がない人が、どんなに素晴らしい声で歌っても、神は喜ばれません。
彼らは信仰で始まり、信仰に進み、最後まで信仰で歩む人達です。生きるにも死ぬにも、信仰を握っていることは、非常に尊いことを覚えて頂きたい。
➀ 信仰をいただいて死ぬことは、明らかに、その人が初めから与えられた神の約束のみことばを信じ続けて、主に贖(あがな)われたことによって、罪が赦され、きよめられていたことを示しています。
② 信仰をいただいて死ぬことは、その人が神に受け入れられていることを証ししています。神の愛を受けて喜んでおり、神の平安に憩っていたことを表しています。
③ さらに、信仰をいただいて死ぬことは、復活の希望をもたらします。
イエス様が再臨される時、その人はよみがえり、主とお会いするわけです。
そのために眠りについたのです。死の苦しみや悲しみは、さらに優れた状態でよみがえるための、産みの苦しみでしかありません。ですから、私は先の聖徒たちにならって、主の恵みによって信仰の道を歩み通し、見えるところや目の前の苦しみが多くても、この信仰の道をもっともっと、もっともっと輝いたものにして歩み続けて行かなければなりません。幸いなことに、私たちは、この信仰の道を歩み続けているわけですから、感謝させていただきたいと思います。
そして、今一度ここで、私たちの信仰の導き手であり完成者であるイエス・キリストを見上げさせていただきたいと思います。
御国の栄光の中にある聖徒たちは、私たちの信仰の姿を見ているでしょう。
私もおなじ信仰を持って、歩ませていただきたいですね。
「はるかにそれを見て喜び迎え」とありますが、「はるかにそれを見て」という表現は、旧約の預言的感覚をよく表しています。
旧約聖書のヘブル語の預言的用法は、遠い山波をカメラの望遠レンズで見るように、実際は遠いのだけれども、すぐ近くに見えるように映しだされます。それがヘブルの預言的用法であります。それゆえ、旧約の聖徒たちは、何千年も先に実現する天の故郷、はるか未来のことを見ていたのですけれども、それで、「はるかに」と書かれていますが、それがあたかも、手元にあるかように見えていたのです。
この気持ちが分かるでしょうか。なかなか現代人には分からないかもしれません。
はるかに見えることは知ってはいるんですが、それが、現実のたましいの経験として、身近に体験していた、ということですね。架空のものを見ていたのではありません。
今は架空の話がいっぱいありますね。架空の話というのはみんな嘘の話であります。
根拠のないものを見ていたのではありません。なぜそういうことができるのかというと、自分のうちにある神の御国を持っていたからですね。はるかな天の故郷を身近に見ることができるのです。
マルコ1章15節を見てみましょう。
マルコ1:15 「時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。」
「神の国は近くなった」というのはキリストの来られたことを言っています。
同じマルコの12章34節も読んでみましょう。
マルコ12:34 イエスは、彼が賢い返事をしたのを見て、言われた。「あなたは神の国から遠くない。」それから後は、だれもイエスにあえて尋ねる者がなかった。
「神の国に遠くない」と言いました。まだ心の中に受け入れていない、でもイエス様に近づいていることを言っています。
マタイ6章33節も読んでみましょう。
マタイ6:33 だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。
私も自分の内に、神の国と神の義を持つなら、未来にある天の御国を身近に見ることができる様になってきます。
そして喜び迎えることができると書いてあります。「喜び迎える」とは、天の御国を前味わいすることです。天の御国をうちに経験しているということです。
パウロはピリピ3章7節~9節でこう言っています。これが天の御国の前味わいです。
ピリピ 3:7 しかし、私にとって得であったこのようなものをみな、私はキリストのゆえに、損と思うようになりました。
3:8 それどころか、私の主であるキリスト・イエスを知っていることのすばらしさのゆえに、いっさいのことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらをちりあくたと思っています。それは、私には、キリストを得、また、
3:9 キリストの中にある者と認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち、信仰に基づいて、神から与えられる義を持つことができる、という望みがあるからです。
キリストを知っていることの素晴らしさ、味わっているということですね。
パウロもまた、イエス様をうちに経験した人です。私もまた、まず自分のうちに神の国をもって喜びましょう。信仰を働かせなければ、神を喜ばせることはできないし、私自身も喜ぶことはできません。私が喜ぶためには、神の喜びを私の内に持つしかないんです。
先ほども詩篇16篇8節9節でダビデはこう言いました。
詩16:8 私はいつも、私の前に【主】を置いた。【主】が私の右におられるので、私はゆるぐことがない。 16:9 それゆえ、私の心は喜び、私のたましいは楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。
喜びと楽しみと平安が満ちていますね。ダビデもパウロも天の御国の前味わいをしています。自分の内に主を持ち、神の国を味わっていたからですね。喜びと楽しみと、安らかさを味わっています。これこそ、天の御国にある神様の恵みの前味わいであります。
ですから、信仰を、天の御国にしっかり向けて、その信仰の道をしっかり歩ませていただきたいと思います。
この世の旅路で受ける困難や課題はあると思いますけれども、イエス様の恵みを経験させていただきたいと思います。
最後にヨハネ16章33節をお読みして、終わりたいと思います。
ヨハネ16:33 わたしがこれらのことをあなたがたに話したのは、あなたがたがわたしにあって平安を持つためです。あなたがたは、世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。わたしはすでに世に勝ったのです。
お祈り
恵み深い天のお父様、私たちもまた、地上を歩いている旅人、寄留者でありますが、しかしイエス様を内に宿すことによって、天の御国の前味わい、憧れを持つことができ、遠い先のことのように見えていますけれども、実際に私たちの内に天の御国が住んでいて与えられていることを感謝いたします。
ですから、聖書に書いてあることは、私たちの内側で体験して生活できますことを感謝いたします。
今週もまた今月も、様々なことが起きてくるかも分かりません。
しかし、どういうことがあっても、さらに今の患難よりも素晴らしい神の栄光が待ち受けていることを経験しながら、一日一日を歩ませてください。
尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
地の塩港南キリスト教会牧師
眞部 明
音声と文書:信仰の列伝(全51回)へブル人への手紙11章 目次
<今週の活用聖句>
詩篇16篇8~9節
「私はいつも、私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私はゆるぐことがない。それゆえ、私の心は喜び、私のたましいは喜んでいる。私の身もまた安らかに住まおう。」
地の塩港南キリスト教会
横浜市港南区上永谷5-22-2 TEL045(844)8421