音声+文書:信仰の列伝(19) 天の故郷をあこがれる信仰(2) へブル人への手紙11章13~16節
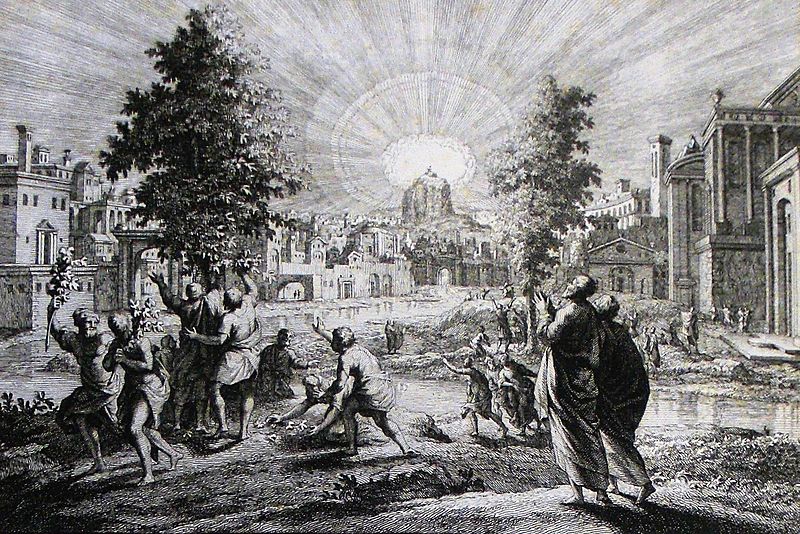
2016年11月20日 (日) 午前10時半
礼拝メッセージ 眞部 明牧師
へブル人への手紙11章13~16節
11:13 これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。
11:14 彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。
11:15 もし、出て来た故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。
11:16 しかし、事実、彼らは、さらにすぐれた故郷、すなわち天の故郷にあこがれていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。
はじめの祈り
「これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。」
恵みの深い天のお父様、こうして私たちも、この年、イエス様のお降りくださったクリスマスの節季を迎えることができまして感謝いたします。
私たちもまた、この地上では旅人であり寄留者であります。
しかしまた、天の故郷、優れた故郷をめざして歩んでいる者でありますので、今日も信仰を強めて下さり、豊かな恵みと助けを与えられて祝福をお与えください。
信仰を新たにして、イエス様とお交わりできる礼拝が捧げられますように。
尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン
前回は、13節の「地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです」の部分をお話できませんでしたので、今日はその部分からお話を始めたいと思います。
「地上では旅人であり寄留者である」ということは、この地上の生活を卑しく思っていたとか、軽んじていたとか、疎んでいたとか、そういう意味ではありません。
パウロは地上の生活と天上の生活について、次のように言いました。
ピリピ 1:21 私にとっては、生きることはキリスト、死ぬことも益です。
1:22 しかし、もしこの肉体のいのちが続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか、私にはわかりません。
1:23 私は、その二つのものの間に板ばさみとなっています。私の願いは、世を去ってキリストとともにいることです。実はそのほうが、はるかにまさっています。
1:24 しかし、この肉体にとどまることが、あなたがたのためには、もっと必要です。
地上の生活において豊かな実を結ぶことが目的である、天の御国を一人一人が獲得するためである、と言っていますね。
肉体にとどまっていることには、迫害があり、苦難があり、いろいろな問題が残りますけれども、個人としては主とともにいることが幸いである。そのことは分かっているけれども、なお今、使命が残っていることを告白しております。
私たちは地上を去るにしても、地上に残るにしても、実を結ぶ生活を、天の御国の栄光を求める、そういうことを目的にしている、と言っています。
ヘブルの11章9節では、「信仰によって、彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束をともに相続するイサクやヤコブとともに天幕生活をしました」と言っています。これはアブラハムたちが、この世の富や力に執着せず、心がとらわれず、この世の生活を永遠の住まいとせず、一時の宿りとして、天の故郷に向かって帰る旅人であることを告白していた、と言っています。それゆえ、アブラハムたちは、この世の財産、力、功績、地位を人と比べて、高ぶったり、自己卑下したりすることから解放されていました。
しかし、
・マタイ19章の金持ちの青年は、神の愛によって心が解放されることがなく、自分の富によって心が縛られていました。
・紫の衣を着た金持ちも、貧しいラザロに愛を施すことをせず、自分の贅沢な生活にだけ心が奪われていました。
・豊作の収穫を得た農夫でも、自分だけが飲み食いすることに心が囚われております。
そういう人々が多い中で、良いサマリヤ人の話では、人種的偏見にとらわれず、自分の持ち物も金銭も、手間も暇も、面倒くささにもとらわれず、傷つけられた見知らぬユダヤ人に愛の手当てを施しています。同じ人間なのに、この違いはどこから来るんでしょうか。信仰の大きな価値というか、目的というか、このあたりに見られると思います。
これはユダヤ人の祭司やレビ人のように、律法を守っていたからではなくて、心に神の愛を持っていたからであります。心に神の愛、アガペを持っているかいないかで、その違いが出てきてしまいます。ですからイエス様は、あの有名なことばを語られました。
マタイ22章37節から39節を読んでみたいと思います。
マタイ22:37 そこで、イエスは彼に言われた。「『心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。』 22:38 これがたいせつな第一の戒めです。
22:39 『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ』という第二の戒めも、それと同じようにたいせつです。
このことばは有名ですけれども、これは天の故郷をめざす信仰の本質を示しています。
結局アブラハムもこの信仰を持っていたので、地上で旅人の生活を続けられたのです。
地上で旅人の生活を続けたということは、甥のロトが自分の所有地を得ようとするときに、選ぶ権利に優先権を与えています。また、愛する子イサクをモリヤの山で、全焼のいけにえに捧げるように命じられた時、従っております。それはアブラハムが、マタイ22章37節~39節の神の愛の信仰を持っていたからですね。これがあるとないとでは、人間の生き方に大きな違いが出てきてしまいます。
アブラハムはこの地上の生活が、旅の途中であることをわきまえていました。この地上の生涯に、終着点があると考えていたのではありません。そのことを、ことばによっても、選択によっても、行動によっても、生活によっても、告白し続けております。
この信仰の表現は、他人への証しとなるし、また、自分自身の信仰を保ち続けるために必要です。私たちが証しをするのは、他の人に伝えるだけではなく、自分自身の信仰を堅くするためにも必要です。証しをしなかったら恵みを失う、そういう危険にさらされてしまいます。万が一にも、この世の富に囚われ、天の故郷を失ってしまうからです。
マタイ16章25節、26節を読んでみましょう。
マタイ16:25 いのちを救おうと思う者はそれを失い、わたしのためにいのちを失う者は、それを見いだすのです。 16:26 人は、たとい全世界を手に入れても、まことのいのちを損じたら、何の得がありましょう。そのいのちを買い戻すのには、人はいったい何を差し出せばよいでしょう。
私たちも、自分たちの実際生活を通して、地上では旅人であり、寄留者であることを証しし告白したいと思います。この地上で財産をため込んで、それを生きがいにする人は少なくないでしょうけれども、ほとんどの人がそうかもしれませんが、それによって、永遠のいのちを失い、神の国を失い、天の故郷を失ってしまいます。
確かに、天幕で移動する生活は不便です。マンションのような立派な家で生活することは、空調も効いて快適かもしれません。天幕生活では不自由かもしれませんけれど、つぶやかず、天の故郷をあこがれて、慕い待ち望む生活をさせて頂きたいと思います。
しかし、他国人のように旅人として、寄留者として歩くのですから、見知らぬ地で過ごすわけです。だから迷いやすいし、曲がりやすい。人の教師の言葉に惑わされやすいし、サタンにも惑わされやすいのです。大方の方は、教会に行っているから、聖書を読んでいるからと安心しているかもしれませんけれども、それでも惑わされやすい。
使徒の働きの17章11節に、ベレヤのクリスチャンたちは、日々に、聖書どおりかどうか調べていた、と言います。それは真理の道からそれてしまいやすいからですね。
私たちは、聖書を読むのは、義務としてではなくて、神の道を歩むためです。真理から外れて自分勝手な聖書の解釈をしている人は、非常に危険である、ということです。このような人は少なくないですね。
たとえば使徒の働きの18章24節~28節で、ユダヤ人アポロのことが書いてあります。アポロは雄弁で熱烈な説教者でありましたけれども、彼が知っていたことは、バプテスマのヨハネの悔い改めのバプテスマであります。悔い改めのバプテスマしか知らなくて、聖霊を受けていませんでしたから、彼のメッセージを聞いて最初に信じたエペソの信者たちは、アポロの説教しか聞いていませんでしたので、熱心に罪の悔い改めの生活をしましたけれども、聖霊を受けることができませんでした。ですから、非常に悩んでいたわけです。
パウロがエペソに来て、エペソの信者たちを見た時、その事実をすぐに悟りました。使徒の19章2節を読んでみましょう。
使徒19:2 「信じたとき、聖霊を受けましたか」と尋ねると、彼らは、「いいえ、聖霊の与えられることは、聞きもしませんでした」と答えた。
「聖霊が与えられることを、聞きもしませんでした」と言っていますが、無理もないことですね。説教者が聖霊のことを知らないのですから。聖霊を受けたことがない。自分で聖霊を受けたことのない人が、聖霊の話をしても同じ結果になります。
今日でも、罪の悔い改めはしているけれども、聖霊を受けて、神の愛と平安と全き救いの喜びを持っている人は少ないのではないでしょうか。
そういう話を聞いたことはある、という人はあるかもしれません。しかし心の中が聖霊に満ちて、神の愛が満ちて、平安に満ちて、救いの喜びに満ちている人は少ないんじゃないでしょうか。
アポロと同じようなことが、少し前のアメリカのオベリン大学で起きています。
オベリン大学の学長だったチャールズ・G・オフィニーは、自分では聖霊の満たしを受けておりましたけれども、彼の説教は悔い改めと全き献身の、激しい熱烈な説教でありました。
それを聞いた神学生たちは、一晩中熱心に、悔い改めと献身の祈りを必死に捧げました。しかし彼らは、信仰の確信も、平安も、神の愛も、聖霊に満たされることも、受けられませんでした。
なぜでしょうか。み言葉と聖霊を信じることを教えなかったからです。
そのゆえに神学生たちは必死に祈ったけれども、安息を得ることができず、疲れ果ててしまったわけです。
パウロはテモテに言いました。第一テモテ6章3節を読んでみたいと思います。あまり読まれないところかもしれませんけれども、とても大事な言葉ですね。
「違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全なことばと敬虔にかなう教えとに同意しない人がいるなら、」と警告していますね。
健全な真理の道から外れてしまうために、こういうことが起きているわけです。聖書のことばを教えている、と言いますけれども、違ったことを教えている。
ある人が私に葉書をくれました。
『私も聖書の話をしているんですけれども、どういうふうに話したらいいでしょうか』
こういう事を葉書一枚で答えを求めようとする人が、世の中にはいるわけです。同じ聖書のことを話しているんですけれども、違ったことを教えている。
イエス様と、敬虔ないのちのことばを教えていない。
私たちが、健全な真理の道から外れないためには、ベレヤの信者のように日々に聖書を調べ、聖書全体を貫いているキリストの贖いの真理からはずれないようにしなければなりません。みことばと聖霊の光に、純真で従順に従っていくことが大事ですね。
私たちは旅人であり、他国に寄留しているわけですから、この世にあっては他国人ですから、毎日生活をしていますけれども、自分の知恵と判断で歩めば道を間違えてしまいやすい。多くの迷い道や落とし穴や誘惑が仕掛けられているのがこの世の中です。そういうところに私たちは住んでいるんだ、ということを忘れてはなりません。
ですから、ヘブル人への手紙にあるように、信仰の導き手であるイエス様から、目を離さないでいましょう。昔、船の航海では、星を見上げて進んだように、私も明けの明星であるイエス様を見上げて進みたいと思います。東の博士たちは、星に導かれて進んで来た結果、イエス様のご降誕に出会っています。
また、イエス様は、マタイ11章29節で「あなたがたもわたしのくびきを負って、わたしから学びなさい。」と仰いました。
イエス様とくびきを共に負っていれば、道を間違えることはありません。このことが生活の中で、実際に行われているかどうかが大事なことです。
自分が好きなこと、好みのこと、自分がこう思うということ、を行っている人、自分の理解と解釈で行なっている人も間違いやすい。自分の知恵と力に頼る人は、道を間違いやすい。
山登りをする時は必ず案内人が付きます。大きな船が港に入る時も水先案内がつきます。私たちも信仰の導き手であるみことばと、イエス様の聖霊を見失うと迷子になります。イエス様は迷子の羊のことを話されましたし、放蕩息子がさまよった記事も記されています。
ですから、寄留者や旅人には導き手は不可欠なことですね。導き手、と言うと、牧師や伝道者を考える人がいますけれども、牧師や伝道者は、聖書が言っている導き手ではありません。私たちの信仰の導き手はイエス様です。
アブラハムもしばしば道に迷いましたけれども、必ず主が現れて、御声をかけて引き戻しておられます。もし自分が道を外れていることに気づいたならば、そのまま行ってしまわないですぐに戻ることですね。
次にヘブルの11章14節を見てみましょう。
ヘブル11:14 彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。
この句はアブラハムの信仰が、言葉や口先だけでなかったことを示しています。
彼ははるか先の、遠い先の、はるかに見えている目的地や、天の故郷を目指していただけではなくて、そういう遠い目的もありますけれども、今日一日の生活を旅人として、手放すものを手放し、受けるものを受けて、目の前の旅人に必要な目的、すなわち、ロトのためにとりなしの祈りをしたリ、ロトの家族を救い出したり、またヘテ人が、妻サラの墓地を無償で差し上げましょう、と言ったときも、将来の争いを避けるために、正当な代価を払っております。本当の細かい信仰のわきまえを活用していることが分かりますね。近隣の部族と争いを起こしていません。
クリスチャンも隣人を愛することをして、争いを起こさないようにしなくてはならない。アブラハムの使用人とロトの使用人が争いを始めた時、すぐにアブラハムはロトに優先権を譲っています。アブラハムにもいろいろと失敗がありましたけれども、日常のこれらの態度や行動は、アブラハムに、旅人としての信仰と、隣人を愛する愛があったことを表しています。
それゆえ、信仰者には、未来の天の故郷の目的と、今日明日の目の前の目的が必要であります。もし、今日の目的を成し遂げる信仰が正しければ、未来の天の故郷に必ず到達します。毎日、今日の一歩が正しければ必ず御国に到達します。心配することはありません。思い煩うことはありません。大事なことは、今日の一日を足の灯、道の光として、みことばを活用することであります。
それゆえ14節のみことばは、アブラハムの今日の信仰の行いを通して、天の故郷を求めることを示した、と言っているわけです。遠い先は天の故郷を目指しているけれども、今日は自分の好きなことをしたい、そういう生活をしていたんじゃないということです。
私たちが、自分を愛するように隣人を愛すること、主に仕えるように人に仕えること、赦しあうこと、助け合うこと、重荷を負いあうこと、今日のようにともに主を礼拝していること、この信仰こそが、天の故郷を求めていることを示しているということです。
ヘブルの11章15節で、「もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう」と言っています。
アブラハムが求めている故郷は明らかに、出てきたカルデヤのウルのことではない。
もし、カルデヤのウルに帰りたければ、いつでも帰ることができたはずです。アブラハムもいろいろと不信仰な失敗をしましたけれども、一度も、カルデヤのウルに帰りたいと言ったことはありませんでした。
エジプトの奴隷生活から、モーセによってエジプトを出てきたイスラエル人たちは、カデシュ・バルネヤでエジプトに帰りたいと騒ぎました。
結局エジプトには帰りませんでしたけれども、40年もシナイの荒野を放浪して、滅びてしまったわけですね。
この世の未信者の生活に戻りたい、それは滅びを招いてしまいます。
イエス様を信じて救われた後、新鮮な喜びを味わった後、きよめの信仰に立って信仰の告白をしていても、自分の生活に活用せず、言葉や口先だけで終わってしまう。
カデシュから不信仰な道を選んだイスラエル人のように、エジプトまではバックスライドしないけれども、荒野をさまよう人は少なくないでしょう。
心の中に、神の愛も、全き平安も、隣人を愛する愛もなく、目の前の目的も、天の故郷の確信もない、そういう生活をしていてはいけないということです。
ヘブル11章16節を読んでみましょう。
ヘブル11:16 しかし、事実、彼らは、さらにすぐれた故郷、すなわち天の故郷にあこがれていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。
この16節を注意深く読んでいただきたいと思います。彼らが、さらに優れた故郷、「天の故郷」を憧れ求めていたことに対して、神は確かに報いてくださっています。
報いは、天の故郷に入るだけではなくて、その前に報いが現れています。アブラハムの求めに対して、答えてくださっていますね。二つあります。
「神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。」これがひとつ、
「神は彼らのために都を用意しておられました。」が二つ目です。
アブラハムたちが、敢えて多くの困難に耐えて、信仰を守り通して、旅人として、寄留者として、生活してきたのは、主が必ず信仰の求めに応じてくださる真実なお方であることを知っていたからです。
私たちは神の真実さを知っているでしょうか。
求める者に対して、神は真実に応えてくださることを信じなければならない、と言っています。
それゆえ彼らの信仰は、この地上の繁栄に執着せず、死を超えて天の故郷を求めています。このアブラハムたちの信仰の悟りの深さには驚かされます。彼らは旧約の人ですけれども、復活を信じております。永遠のいのちを持っていることを自覚していました。
「永遠のいのち」という言葉は新約聖書に出てきますけれども、旧約の人が知らなかったわけではありません。この地上のことがすべてでないことを悟っています。
それに比べて、私の信仰は、この世の問題の解決にふりまわされ、思い出したように天の故郷を求めていないでしょうか。
アブラハムもいろんな問題に振り回されておりますけれども、天の故郷を思うことから外れることはありませんでした。
そこで、アブラハムたちの信仰の内容を、見てみたいと思います。
第一に、神の都を「故郷」と呼んでいることですね。
「故郷」というのは「ふるさと」のことですから、それは「行くところ」ではなくて「帰るところ」です。自分が出てきたところです。
それじゃカルデヤのウルではないかと仰るかもしれませんけど、そうではありません。自分の存在の起源を故郷と言っているわけです。たましいにいのちを与えて下さるのは神様ですから。与えられたたましいの起源を指しております。
私たちのたましいを救いきよめ導いてくださっているのは、主イエス様であります。その主イエス様のおられるところに帰るのが、天の故郷であります。
ヨハネの14章3節で、「わたしが行って、あなたがたに場所を備えたら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。わたしのいる所に、あなたがたをもおらせるためです。」と仰いました。
ですから、主イエスを心に経験している人は、心の中に天の故郷、本能的になつかしさ、憧れ、慕わしさ、安らぎを感じています。まだ天の故郷に行っているわけではありませんけれども、今心の中でその味わいを知っているわけです。
ですから、旧約の聖徒たちは、「神の都」を「行くところ」としてではなく、「帰るべき故郷だ」と言っているわけです。心の中にその憧れを持っているからです。
「神の都」は主イエスを信じる人にとっては、もはや「未知のところ」ではなく、毎日神の国と神の義を求めている人にとって、親しく慕わしいところとなっています。
有名なことばを二つ読んでみたいと思います。
マタイ6章33節「だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。」
多くの人が、「神の国と神の義を第一に求めれば、これらのものはすべて与えられる」というところに最も関心があるようですけれども、大切なことは、神の国とその義を心に持っている人は、天の故郷を味わっている人だ、ということです。
その人にとっては「天の故郷」は知らない所ではありません。行ってみなければわからないところではない。なぜなら、その本質を自分の心の中に持っているからです。
ルカの17章21節も読んでみたいと思います。
ルカ17:21 『そら、ここにある』とか、『あそこにある』とか言えるようなものではありません。いいですか。神の国は、あなたがたのただ中にあるのです。」
「あなた方のただ中に」というのは「あなた方の心の中に」ということですね。
神の国を持って営んでいる、生活の中にある、と言われたのです。心の中に神の国を持って生活し、実際生活を神の国に相応しい生き方をする時、神の国はもはや、まったく未知のところではなくなります。
親しい、慕わしい、懐かしい、憧れのところとなり、その神の都はたましいの故郷となり、「行くところ」ではなく「帰るところ」になります。自分の内に持っている神の都を、具体化したところに帰るわけです。私たちは、天の故郷に入る切符を持っているだけではなくて、その味わいも持っているわけであります。
彼らははっきりと、自分たちが出てきた地上の故郷と、天の故郷を区別しています。
聖書はこう言っているんです。「もし、彼らが望むなら、その地上の故郷、すなわち異教の地、カルデヤのウルの生活でも、パダン・アラムのカランの生活でも、すぐに戻ることができたでしょう。しかし、そうしなかった。彼らは旅人の生活で多くの苦難に出会ったのに、どうして異教の生き方に帰って行かなかったのか。もし、彼らが地上の繁栄を求めていたのなら昔の生き方に帰って行ったでしょう。しかし、帰らなかった。」
信仰生活をしていて、いざとなった時、本当はこの世の富も欲しかった、地位も、学歴も欲しかった、あれもこれも欲しかったと言い出す人がいました。その人の信仰は一体何だったのでしょうか。本音の部分で、天の故郷ではなくて、出て来たこの地の故郷を求めている。
クリスチャンの中でも途中で信仰を捨てて、異教の地に帰ってしまう人がいます。それは、彼らが優れた天の故郷を知らない。口では「神の国とその義を求めている」とは言いますけれども、たましいでそれを味わっていない。地上の安逸を求めていたから、目の前の困難を逃避して不信仰者になってしまいます。
これらの人に対して、ペテロは次のように警告しています。
Ⅱペテロの手紙2章15節と16節を読んでみましょう。
Ⅱペテ 2:15 彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。
2:16 しかし、バラムは自分の罪をとがめられました。ものを言うことのないろばが、人間の声でものを言い、この預言者の狂った振舞いをはばんだのです。
ちょっと飛びますが20節も読んでみましょう。
Ⅱペテ 2:20 主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れからのがれ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は、初めの状態よりももっと悪いものとなります。
サタンに従うこの世の宗教は、必ずこの世の繁栄をうたって誘います。こうすればどうなる、ああすればああなる、と言います。
サタンがイエス様を誘惑した時も、この世の国々の栄華を見せました。サタンは、「私を礼拝すればこれをあげよう」と言いました。それがいつもサタンのやり口ですね。
それは偽りの罠であります。偽りの罠は、いつもそのような、肉の欲を満足させるものを提供しています。ですから、そういう物に心を引かれている人は、それを宗教だと思って、殆ど今の世の中はそうなっていますが、それに惑わされてしまいます。
真の信仰は、今の生活から天の故郷を味わわせてくれます。前味わいをさせてくれます。天の故郷を望ませてくださる、そういう信仰でなければ信じるに値しません。
アブラハムたちは天の故郷を求めていただけではなく、「あこがれていた」と書いてあります。これは単なる求めよりも、もっと強い動機を示しています。熱望していた、ということであります。この世の苦しみから逃れるためにイエス様を信じている、そのような程度の信仰ではなかったということです。
私たちは、死をも滅ぼしてしまう比類ない、永遠に価値のある天の故郷、神の国、神の都の味わいを経験する時、どんな苦難をも耐え抜くことができるし、死を乗り越えて、天の故郷を求めるようになります。
マタイ13章44節~48節をお読みしたいと思います。
マタイ13:44 天の御国は、畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。
13:45 また、天の御国は、良い真珠を捜している商人のようなものです。
13:46 すばらしい値うちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。
13:47 また、天の御国は、海におろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。
13:48 網がいっぱいになると岸に引き上げ、すわり込んで、良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。
マタイの13章は、天の御国がずらりと並んでいる所であります。
神の国は、「畑に隠されている宝のようなものです」とありますが、偶然に見つかるものではありません。「隠されている」とありますが、誰かが「隠した」わけですね。神様がお隠しになっている。「隠してある」と書かれているのは、探すことが必要だということです。
私たちは聖書を読んだら分かるようになるわけではありません。そこで掘り返して、探さなければならない。網で魚を取っている話もありますけれども、岸に引き上げると、良い物と悪い物をより分けていますね。そういうことも必要だということです。より分けなくてはならない。より分けないと真実なものを見出すことができません。
私たちはすでに、この土の器に宝をもっているわけであります。良い真珠を見つけています。だったらそれを毎日使いましょう、活用しましょう。
苦難が苦しく感じる時は、心に失望感が入り込んでいる時です。主から目を離して不信仰が忍び込んでいる時です。そういう時は主イエスを仰ぎ見ることが必要ですね。
主は、最後まで主を信じ続け、天の故郷を求め続ける人に、どんな報いを与えているか、それは先ほど読みました2つであります。
➀、第一の報いはヘブル11章16節で、「それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。」
神は、アブラハムの神、と呼ばれることを誇りとされました。
神は、モーセの神、と呼ばれることを誇りとされました。
神は、ヨブの神、と呼ばれることを誇りとされました。
主は、私の神、と呼ばれることを誇りとしてくださっているでしょうか。そのように信じたいですね。
それでは、主は、どのような人を恥とされるんでしょうか。
マルコ8章38節を読んでみましょう。
マルコ8:38 このような姦淫と罪の時代にあって、わたしとわたしのことばを恥じるような者なら、人の子も、父の栄光を帯びて聖なる御使いたちとともに来るときには、そのような人のことを恥じます。」
イエス・キリストとイエスのみことばを恥じる者を、キリストの再臨の時に恥じると言いました。
イエス様の再臨の時だ、と言ったら、ずいぶん先のことではないかというかもしれませんが、しかしそれは、決定的な時に恥じる、ということです。
まだ時間があるからいいじゃないかという人がありますが、私たちは今のうちに、神様のみことばに忠実に歩むようになりたいものです。
私たちは、イエス様と、イエス様のみことばを力強く証しさせていただきましょう。
そうすれば、主は、私たちの神と呼ばれることを誇りとされます。
②、第二の報いは、ヘブル11章16節の「事実、神は彼らのために都を用意しておられました。」です。
ヨハネの14章2節から3節をお読みしたいと思います。注意して読んでください。
ヨハネ 14:2 わたしの父の家には、住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなたがたに言っておいたでしょう。あなたがたのために、わたしは場所を備えに行くのです。
14:3 わたしが行って、あなたがたに場所を備えたら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。わたしのいる所に、あなたがたをもおらせるためです。
ここでは、住まいはまだ建設途中のような言い方をされています。けれども、ヘブル11章16節では、「都を用意しておられました」と過去形で語られていることに注意してください。もう今は、建設途中ではないということです。これは、神の都の確実性を強調しています。ですから、いつでもお迎えに来てもよい状態になっていることが分かります。
私たちは、今日、神の国と、天の故郷を心に持って味わい、日々の生活を営み、証しをさせていただきたいと思います。
そして毎日、御国を慕わしい味わいをしながら、今日の生活を営ませていただき、そのこと自体が私たちにとって大きな宝であります。
そういうことを私たちが毎日経験するたびに、隠されている宝を見出す生活をさせていただいて、そのことが私たちの周りの者たちの心にも光となって、喜びとなって届いていくように、証しをさせていただきたいと思います。
お祈り
恵みの深い天のお父様、すでに私たちは、神の国とその義とを与えられて、天の故郷の前味わいをさせていただいていることを感謝いたします。
それゆえに天の都、天の故郷は、私たちにとって知らない所ではなくて、非常に慕わしい、喜びに満ちたものであります。そこに私たちが帰っていくための、毎日の信仰の働きをさせていただいております。
これからもあなたの道をまっすぐに歩んでいくことができ、その喜びの証しをさせていただけますよう顧みてください。
今月はイエス様のご降誕の節季でありますけれども、私たちのうちに住んでくださるイエス様を十分に味わわせていただき、信仰の光を輝かすことができますように。
尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
地の塩港南キリスト教会牧師
眞部 明
音声と文書:信仰の列伝(全51回)へブル人への手紙11章 目次
<今週の活用聖句>
へブル人への手紙11章16節
「しかし、事実、彼らは、さらにすぐれた故郷、すなわち天の故郷にあこがれていたのです。それ故、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。」
地の塩港南キリスト教会
横浜市港南区上永谷5-22-2 TEL/FAX 045(844)8421

