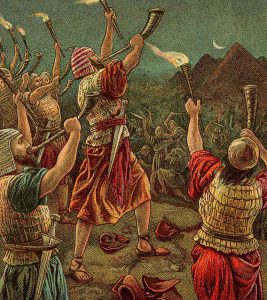音声+文書:信仰の列伝(33) バラクの信仰 へブル人への手紙11章32~34節

フランスの画家James Tissot (1836–1902)による「Jael Shows to Barak, Sisera Lying Dead(ヤエルは、バラクにシセラが死んで横たわっているのを見せる)」(Wikimedia Commonsより、Jewish Museum蔵))
2017年3月26日 (日) 午前10時半
礼拝メッセージ 眞部 明牧師
へブル人への手紙11章32~34節
11:32 これ以上、何を言いましょうか。もし、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば、時が足りないでしょう。11:33 彼らは、信仰によって、国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口をふさぎ、11:34 火の勢いを消し、剣の刃をのがれ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。【新改訳改訂第3版】
はじめの祈り
「弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり」
恵みの深い天のお父様、こうして、私たちの日ごとの生活や戦いを支えてくださって、今日もまた、新しい礼拝をささげて、新しいいのちをいただいて、恵みをいただいて進めますことを感謝いたします。
みことばを祝してくださり、今日もイエス様とお会いして、新しい門出を迎えることができますことを感謝いたします。
みことばを祝し、聖霊を与えられて、私たち一人ひとりを新しくしてください。心からお願いします。この時を主の御手にゆだねて、尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日は信仰の列伝第33回目ですが、「バラクの信仰」をお話ししたいと思います。
バラクは、ナフタリ族の将軍の一人でしたが、前回お話ししたギデオンと同様に、「信仰の勇者」と呼ばれるには程遠い人物でした。そのバラクから何を学ぶことができるのか、今日はそのことを探りたいと思います。
私がバラクから学ぶことは、この世の力、つまり、武力や地位やお金の力などでは、決して勝利が得られないことを教えられます。
人格の破壊や、家庭の崩壊、絶望や死などは、それに直面する時に、将軍の地位もお金の力も、なんの支えにも助けにもならないことが分かります。人間は無力であることをつくづく教えられます。私が生まれながらに持っている力は、自分の欲望をわずかに、しかも一時的に満足させることしかできません。
そこでまず、イスラエル人の前にはどんな困難が横たわっていたかを、あげてみましょう。課題が二つありました。
第一の課題は、士師記の4章1節の後半で「エフデは死んでいた」とあります。イスラエルの民が、神様が遣わされた指導者を失っていたことが分かります。聖書は時々、モーセが死んだ後とかに、強力な指導者がいなくなってしまったその後に、残された者たちの姿を表している所があります。
時代が変わっていく。神様は変わりませんけれども、人の時代が変わっていく。イスラエルの民は、指導者を失っていました。
これまでの世界の歴史を考えると、強力な霊的指導者を持っている間は、その国は栄えます。国が強力な力を持ち繁栄しますけれども、その平和な時代が長く続くと、国民は主を求めなくなってしまって、堕落が始まり、どんなに力を誇っていた帝国も、衰退し滅んでいきます。それが人間の歴史であります。
士師記の特徴は、モーセとヨシュアという非常に強力な指導者を失ったイスラエルの民が、平和と繁栄のもとで偶像礼拝に堕落し、衰退していく姿を描いています。
モーセは、神のご命令を声高く民に語り、教え続けました。ヨシュアはモーセの働きの強力な影響の下で、カナン人と戦い、勝利を収めて行きました。そういう指導者が、次々と現れるかどうかということは、非常に重要な事です。強力な指導者がいる間はイスラエルの平和と繁栄の基礎を築きました。しかし、イスラエルの民は、その上に安堵して、だんだんと、神のみことばを求めなくなってしまいました。指導者がいる間は求めていても、指導者がいなくなると、神を求めなくなってしまいました。
そして、士師記の時代を見ると、神のことばを強力に教える預言者も出てきておりません。イスラエルの民に堕落を警告するのは、近隣の異教の侵略者たちが侵入してくるという情けない状態に陥っております。近隣の侵略者が入ってくることによって、イスラエルの民は、自分たちが偶像礼拝していることを責められるわけですね。もはや、神の民は、自分で立ち直ろうとする、自戒し自立する力を失っていたのであります。人から言われて、はっと気が付くというような状態になっていた。自分の力で、自分の信仰で、立つことができない状態になっています。士師記の時代のイエラエルの民は、そういう状態に陥っていました。
クリスチャンが神のみことばに飢え渇き、みことばの水を飲み、みことばの糧を食べる様になる時に、力を発揮するようになります。
教会が、儀式やイベントを行うことに忙しくなって、ペンテコステの教会がパンを配ることに忙しくなって、神のみことばをおろそかにした時に、お互いの間に不平や不満や争いが始まりました。聖書のみことばに真剣に取り組まなくなる時、みことばを聞くことの飢饉が襲ってまいります。
そして今現在も、その飢饉が襲ってきているんではないでしょうか。聖書の真理が何を語っているのか、分からなくなっている牧師や教師が増えてきていないでしょうか。聖書をどう解き明かせばいいか、分からなくなってしまっていないでしょうか。
こうしてイスラエルは、だんだんと神のみことばを失うようになり、致命的な問題に直面していたわけであります。
この問題の解決は、イスラエルの最後のさばきつかさと言われている、サムエルが生まれるまで待たなければならなかったのです。
サムエルはこのことに気付いて、神の御声を聞くことができるダビデを育てました。さらに、預言者学校を開いて、エリヤやエリシャが育ち、イスラエルの民を救ったのです。
世の中は、聖書の言葉をないがしろにしていますけれども、神のみことばを取り次ぐ預言者は、どうすれば育つのか。私たちは、このことを真剣に求めなければならないでしょう。
マタイ7章24節を、読んでみたいと思います。このことばは、何回も何回も読む必要がありますね。
マタイ7:24 だから、わたしのこれらのことばを聞いてそれを行う者はみな、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。
確かに、聖書は読んでも分からないものです。分かったように思えても、真理の奥義まで届いていないことがよくあります。それ故、健全で分かりやすい信仰の手引が必要になってきます。
そこで、私は「聖書の探求」を、30年以上も書き続けてきましたけれども、これによって、聖書が分かるようになった、と言ってくださる方もおられます。
しかし、何と言っても、聖書をじかに読んで、神の御声を聞いてくださるようになることが大事です。
すべてのイエス・キリストを信じている信仰者は、神の子としてくださる霊を受けていますから、「アバ、父」と呼んで、神の御声を、神様のみこころを、光を、受けるようになります。
これは私の努力によってではなく、神の御霊によってできます。心の目が澄まされて、信仰の耳を傾けて聖書を読めば、主の語り掛けが届いてまいります。 自分のたましいの内に、神様のみわざが経験できるようになってきます。こういう人が増えてくることが、大事なんですね。
神のみことばが、求められなくなることは、最大の危機が来ていることを意味しています。
イスラエルの第二の課題は、民が再び、主の目の前に悪を行っていたことです。
神の民なのに、主に立ち返っては、また再び主の前に悪を繰り返す。これは明らかな原因があります。
士師記4章1節の前半に、「その後、イスラエル人はまた、主の目の前に悪を行った。」と書いてあります。
士師記の中には、「主の目の前に悪を行った」という文言が、繰り返されています。立ち直っては、また繰り返す。これは、単なる過ちとか失敗を犯した、というのではありません。明らかに、神様が禁じておられるカナンの偶像礼拝をおこなっていたことであります。それを取り除いては、また祭壇を築く、祭壇を築いて偶像礼拝を行う、これを繰り返すことによって、神の怒りを招いています。
今も、この警告は働いています。神の民の堕落は、表面的に見ていても分かりません。真面目で正しく、熱心なように見えても、人の目には見えない自分中心の自己義を押し通したり、罪の性質が残っていたりする限り、同じ罪を繰り返してしまいます。神の前に悪を行なうことは、自分を堕落させ、最も愚かな敗北者にしてしまいます。
この事実は、私たちのたましいが、お金や才能や健康で生きているのではなく、イエス様が仰ったように、私たちのたましいは神によって造られた霊的な存在であり、神のみ口から出る神のみことばを食べて、日々に生きているわけであります。その神様のみことばを食べなくなったら、たましいは死んでしまいます。
士師記に見られるイスラエルの民の特徴は、神の器によって信仰が回復しても、再びまた神の前に悪を行う、堕落を何回も繰り返しているのです。神の民であるのにそれが繰り返されているところに最大の原因が見られます。
そして、それを繰り返すたびに、神の国の国力が衰えていっている。イスラエルの国が衰えていっています。
このことは、きよめられていないクリスチャンによく似ています。
罪を繰り返すたびに、サタンの侵入が心に深く食い込んできて、サタンの影響が強くなり、ついに主イエスから離れてしまう人が少なくないんです。
十二弟子の一人だったイスカリオテのユダでさえ、サタンの侵入を受け続けて、ついに主を裏切る者となりました。他の弟子たちは、そこまで主を裏切らなかったけれども、全員、主を捨てて逃げ出してしまっています。
マタイ26章35節を読んでみましょう。
マタイ26:35 ペテロは言った。「たとい、ごいっしょに死ななければならないとしても、私は、あなたを知らないなどとは決して申しません。」弟子たちはみなそう言った。
これはただの熱心による努力というよりも、必死のことばです。
ですから、人の熱心、決心、努力、告白が、どんなに熱いものであっても、簡単に崩れ去ってしまうものです。そういう決心や告白を、当てにしてはならない。イエス様はそれを見抜かれました。
34節をちょっと読んでみたいと思います。
マタイ26:34 イエスは彼に言われた。「まことに、あなたに告げます。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度、わたしを知らないと言います。」
ペテロは、そのとおり三度主を否定してしまいました。そんなはずではなかったわけですが、これは、聖霊に満たされていなかったペテロが、いかに危険な状態であったかを表しています。きよめられていない、ということは、単に信仰が不足しているということだけではないですね。非常に危険な状態にある。
話を士師記の方に戻します。
士師4:2 それで、【主】はハツォルで治めていたカナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡した。ヤビンの将軍はシセラで、彼はハロシェテ・ハゴイムに住んでいた。
ヤビンの手に「売り渡した」と書いてあります。「売り渡す」とは、奴隷に売り渡す、という意味があります。これは、神に選ばれた民として、誇り高いイスラエル人にとって大きな屈辱になりました。
こうなる前に神の警告をきいて、自分の罪や高慢を悟って、いち早く悔い改める人は、このような悲劇を味わわなくて済みます。
だんだんと警告が深刻になっていくことが分かります。しかし、大抵の人がことばの警告を聞くと、反発したり反論したりします。
本当は、ことばの警告の時に従うのが幸いなことですね。それを拒むと、主は、次の手段として、痛みの伴う刑罰の懲らしめを加えることになります。ここに至って、クリスチャンも神の民も、後悔したり屈辱を覚えるのです。その結果、イスラエル人は主に叫び求めております。
士師記の4章3節を読んでみましょう。
士4:3 彼は鉄の戦車九百両を持ち、そのうえ二十年の間、イスラエル人をひどく圧迫したので、イスラエル人は【主】に叫び求めた。
「鉄の戦車九百両」は、後でちょっと問題になるので、ここで覚えておいていただきたいのですが、「鉄の戦車九百両」というのは、当時としては、最新の強力な軍事力を意味しています。
今は、愚かなことですけれども、世界中で軍事力を誇る国々が出てきております。人間の愚かさを丸出しにしているような状態ですね。
それによって、二十年間の長い間、圧迫と略奪が繰り返されてきたわけです。
イスラエルは、たまらず主に助けを求めました。
自分中心の人は、自分が平和で繁栄している間は身勝手なことをしていても、自分が苦しくなると、罪を悔い改める事もなく、主に助けを求めて叫びました。主は憐み深いお方ですから、助けてくださいましたけれども、それに甘えて不信仰を繰り返していると、ついには、イスラエルが捕囚によって滅亡したように、取り返しがつかない結果になります。
ここで注意していただきたいことがあります。
イスラエル人は、「主ご自身」を求めたのではなく、主に「助け」を求めて叫んでおります。自分が、わざわいや苦しみから逃れることを求めたのであって、主のご人格を求めたり、主に忠実に従っていくことを求めたのではありません。
私のところにも、いろいろな祈りの依頼がきますけれども、自分が苦しみから逃れるための利己的な祈りであって、主ご自身を求める祈りの依頼はほとんどありません。ですからその苦しみが去ると、顔を見せなくなります。これでは、この世の御利益宗教と同じです。
真の信仰は、「主ご自身」を求めることであって、主に「助け」だけを求めることではありません。
もちろん、主に助けを求めることは、悪い事ではありませんけれども、神様ご自身はいらないけれども、神様の助けだけをもらう、という信仰は成り立たないでしょう。
もちろん、主は憐み深いお方ですから助けてくださいます。苦難やわざわいや病からも助けてくださいます。しかし、それは、主ご自身を自分の内に宿した結果与えられるものです。主に「助け」だけを求める人は、助けが与えられると、再び、主のもとに帰って来ません。
ルカ17章12節から19節で、十人のらい病の人話が出てきます。彼らは全員、イエス様によって癒されましたが、十人の内の九人は、主のもとに感謝のために帰ってくることはありませんでした。イエス様の足元にひれ伏して感謝したのは、サマリヤ人一人だけであった、と書いてあります。
わざわざサマリヤ人のことを書いたのは、ユダヤ人がサマリヤ人を軽蔑していたからですね。そのサマリヤ人だけが、イエス様に感謝をささげ、礼拝をささげに帰って来た。
現在も、この状況は変わっていないのではないでしょうか。多くの人が、悩みや苦しみを抱えて来たのに、主を礼拝するためには、姿を見せていません。
このような時、バラクはどのような信仰を持っていたのか、見てみましょう。
まず彼は、自分から自発的に立ち上がろうとしませんでした。
彼もまた、ギデオンと同じように、屈辱の故に打ちひしがれていました。カナンの王ヤビンの手を、跳ね除けることができる、とは考えなかったのです。悔しくても、不信仰な思いの中に沈んでいました。
この優柔不断な、不信仰な思いがくせものです。この不信仰な思いが、敗北を連れてきてしまいます。敗北には、突然来る敗北もあれば、じわじわ蝕んでいく敗北もあります。このまま不信仰が続いたら、ヨシュアの時の勝利は食い尽くされてしまい、イスラエルは早々と全滅してしまっていたでしょう。
バラクには、神のみことばを聞く霊の力が欠けています。バラクは、自分から神に祈り求めませんでした。
平和で繁栄した社会で暮らしている人は、自分の知恵と力に頼ってしまっています。ですから、苦難の時に、神のみことばを聞いて力を受けて立ち上がることができないんです。そういう人は、どうしたら神の力を受けることができるでしょうか。神のみことばを受けることだけです。他に方法はありません。
そこで主なる神様は、ラビドデの妻で、女預言者デボラを遣わして、バラクに神の御命令を伝えさせています。
私たちにはすでに、聖書が与えられていますけれども、それでも聖霊によって解き明かされて、神のみ声を聞いて、みこころを悟り、真理の奥義を経験する必要があります。聖書を読んで、知識を理解して持っているだけではなくて、神の口から出る、自分に語られた神の御声を聞く必要があります。それを自分の信仰で働かせることができるようになりたいものです。
士師記の4章5節を読んでみたいと思います。
士師4:5 彼女はエフライムの山地のラマとベテルとの間にあるデボラのなつめやしの木の下にいつもすわっていたので、イスラエル人は彼女のところに上って来て、さばきを受けた。
「デボラのなつめやし」という彼女の名前が付いた木があるくらいですから、さばきつかさとしての彼女の名前は、知れ渡っていたことが分かります。人々が、デボラのすわっているなつめやしの木の下にきて、その木に「デボラのなつめやし」という名前を付けたのですね。彼女は、人々が訴えやすいように、いつもその木の下にすわって、人々の訴えを受け付けて、指導していたのです。彼女は女性で、妻の立場にありましたけれども、さばきつかさとして神の働きをするのに、少しの支障もありませんでした。
女王の地位というのは、イゼベルやアタリヤのように、富と権力でその地位を得ることができますけれども、さばきつかさや預言者は、神の任命がなければなることができません。ですからデボラは、神様の任命によっていることが分かります。
このデボラの例を見ますと、神様は、神のみことばを持って働く神のしもべを、緊急に必要としていたことが分かります。私たちの時代でも、全く同じことが言えるでしょう。
デボラは説教はしなかったかもしれません。しかし彼女は、人々から持ち込まれる悩みや、苦しみ、素朴な訴え、いろいろな問題をよく聞き、自分の考えで解決策を話すのではなくて、一回一回、神様のみことばを聞いて、ここに神のみことばがある、と教えて、共に祈る働きをしたようです。
「神様のみことばは、こう言っています。一緒に祈りましょう。」という奉仕なら、聖霊の助けをいただいて、私にもできそうです。全てのクリスチャンに、デボラの働きをしてほしい、というのが神様の求めですね。神様が必要としているしもべは、こういう人なんだ、ということです。
大説教ができなくても構わない。しかし、一人ひとりの悩みや課題をよく聞いて、そして、「神様のことばにこういうのがありますよ。」と言って、共に祈る。この働きをするのに、女性であることも、妻であることも、少しも妨げになりません。
今日、私たちに必要なのは、デボラのような人ではないでしょうか。
そのためには、デボラ自身が主と親しく交わり、絶えず神のみことばを聞いていなければなりません。話すことより、聞くことが大事だと、箴言は言っています。神様の語り掛けをよく聞いて、そういう聖書の読み方をしていれば、何を語ればよいかは、神様がその都度教えてくださいます。悩むことはありません。自分の知恵で考えたことを話すこともなくなります。そして、真理のみことばを、まっすぐに話す人になります。
バラクは武器を使うことができても、神のみことばを聞いている人でもなければ、神のみことばに従っている人でもないので、国民は武器を使っても罪を犯してしまいます。国は衰退し、堕落して、神のさばきを受けることになります。
今の時代でも、核兵器をどんなにたくさん持ったからと言って、その国が強いわけではありません。安全であるわけではない。
デボラがバラクに伝えた神のご命令は、士師記4章6節の後半にあります。
士師4:6・・・・・【主】はこう命じられたではありませんか。『タボル山に進軍せよ。ナフタリ族とゼブルン族のうちから一万人を取れ。
今回は、一万人を取れ、と言っています。ギデオンの時は三百人でありましたから、かなり兵士の数が多い戦い方であります。4章7節では、その意味まで明らかにされています。今回はなぜ一万人なのか。
士師 4:7 わたしはヤビンの将軍シセラとその戦車と大軍とをキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡す。』」
ここで、一万人と言っている所に意味があるわけですね。「引き寄せる」とは、敵の大軍をおびき寄せることを言っています。そのためには、目立つ必要があるわけですね。目立つように、一万人が集められています。
バラクと兵士はタボル山に陣取って、シセラと大軍は低い地のキション川におびき寄せられました。一挙にバラクの兵士を踏み潰す魂胆であります。
ここで注目したいことは、主はバラクに、「タボル山に進軍せよ」、「一万人を取れ」、「彼をあなたの手に渡す」と言われただけです。どこにも「戦え」と命じていないことです。聖書を注意深く読む必要があります。「進軍せよ」、「取れ」、「渡す」と言われただけで、「戦え」と言われていません。
主のご命令は、ただ、恐れずに敵の大軍の前に出て行って姿をみせ、前進すること、だけです。
これは、エリコの戦いによく似ております。バラクがもし、先人のエリコの戦いのことを学んでいたなら、信仰の戦いを学び取っていたはずであります。バラクは体格が立派で強そうでしたけれども、実質はさっぱり駄目な男でした。彼はこのご命令に対して、潔く信仰に立って出ていこうとしませんでした。
士師記4章8節をご一緒に読んでみましょう。
士師4:8 バラクは彼女に言った。「もしあなたが私といっしょに行ってくださるなら、行きましょう。しかし、もしあなたが私といっしょに行ってくださらないなら、行きません。」
信仰がなかったバラクは、女預言者デボラが一緒に行ってくれるなら行く、と言いました。彼は、神様の約束があっても、神の同行を信じる信仰がなかったのです。本当に信仰がなければ、どんなに立派なことを言っていても、人は当てになりません。
士師記4章9節のデボラの答えを見てみましょう。
士師4:9 そこでデボラは言った。「私は必ずあなたといっしょに行きます。けれども、あなたが行こうとしている道では、あなたは光栄を得ることはできません。【主】はシセラをひとりの女の手に売り渡されるからです。」こうして、デボラは立ってバラクといっしょにケデシュへ行った。
情けない話ですけれども、デボラは「行ってくれる」と言ったんです。
一緒に行きますけれども、敵は彼の手に落ちない。後で話しますけれども、神様は一人の女の人を備えられていて、神様の御業を現わします。行くことは行くけれども、あなたは光栄を得ることはできません、と言いました。
ヨハネの11章40節をご一緒に読んでみたいと思います。ベタニヤのマルタとマリヤに、イエス様が話された言葉ですね。
ヨハネ11:40 イエスは彼女に言われた。「もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る、とわたしは言ったではありませんか。」
最後まで自分の信仰で立てなかったバラクは、戦いに勝つことは勝っても、神の栄光を受けることができませんでした。
私たちはみんなで一緒に信仰の働きをしているかもしれませんけれども、一人ひとりが信仰で立って信じていなければ、その人は神の栄光を経験することができない。最後まで自分の信仰で立てなかったバラクは、戦いに勝っても神の栄光を得ることができませんでした。
こういうバラクが信仰の列伝に出てくるのは矛盾していますけれども、こういう人でも、信仰の弱い人を助けて、勝利に至る証しになるので、取り上げているようです。
ローマの15章1節には、こうあります。
ローマ15:1 私たち力のある者は、力のない人たちの弱さをになうべきです。自分を喜ばせるべきではありません。
信仰の弱い人であっても、助けを受けることによって、みことばで励まし、祈り、一緒に戦うことによって、勝利に至ることを証しすることができます。
士師記4章10節では、
士師 4:10 バラクはゼブルンとナフタリをケデシュに呼び集め、一万人を引き連れて上った。デボラも彼といっしょに上った。
4章12節、13節では、これを聞いたカナンの王様ヤビンの将軍シセラは、タボル山の南側のふもとの低地、キション川に陣を敷きました。
士師4:12 一方シセラは、アビノアムの子バラクがタボル山に登った、と知らされたので、
4:13 シセラは鉄の戦車九百両全部と、自分といっしょにいた民をみな、ハロシェテ・ハゴイムからキション川に呼び集めた。
このキション川の付近は、やがて、この世の終末の裁きの直前に、神の敵対するこの世の王たちの戦いの戦場になることが預言されています。ですから、この場所は、歴史的に特別な意味があるということが分かります。
ヨハネの黙示録16章16節に、「ハルマゲドン」という言葉が出てきますが、「ハルマゲドン」というのは、メギドの丘、という意味であります。このメギドはキション川の近くにあります。この付近は、バラクの時代から、無数の人間の血を吸い込んでいる場所です。そこが最後の戦いの場所になると、ヨハネの黙示録はそのことを記しているわけです。
さて、バラクはタボル山に着いても、敵の軍隊をおびき寄せるために出ていこうとしませんでした。臆病だったからですね。
デボラは、行くように言いました。うながし、やっと、腰を上げました。
4章14節を読んでみたいと思います。
士師 4:14 そこで、デボラはバラクに言った。「さあ、やりなさい。きょう、【主】があなたの手にシセラを渡される。主はあなたの前に出て行かれるではありませんか。」それで、バラクはタボル山から下り、一万人が彼について行った。
何度も言うようですけれども、バラクもギデオンと同じように、神様のみことばの約束だけでは確信が持てない、非常に弱い信仰の持ち主でありました。信仰があるかないか、分からないような状態であります。4章15節も読んでみましょう。
士師 4:15 【主】がシセラとそのすべての戦車と、すべての陣営の者をバラクの前に剣の刃でかき乱したので、シセラは戦車から飛び降り、徒歩で逃げた。
バラクの兵士たちがタボル山を駆け下り始めると、主がシセラとその軍隊をかき乱した、と書いてあります。この結果を見ると、バラクは、何を恐れることがあったんでしょうか。彼はただ、戦う前の、ヤビンとシセラの大軍を見て、それを恐れていただけであります。もし、バラクが敵の大軍を見ずに、主のみことばを心に留めていたならば、もっと平安に、確信を持って進むことができたでしょう。ペテロがガリラヤ湖で、イエス様から目を離し、嵐の風と波を見た時、水の中に沈みかけたのと同じです。
私たちの心が、心配事でいっぱいになっていると、その心配した通りになってしまいます。沈みかけてしまいます。しかし、心の中に、すでにこの世に勝ってくださったイエス・キリストが満ちてくださるならば、みことばを握って歩むだけですね。必ず栄光を現わしてくださいます。
不信仰で臆病なバラクは、才能も能力も武力もありましたけれども、神のみことばに従う信仰がないために、恐れて不安になり、信じてやってみないで敗北している人の姿であります。
私たちは、聖書の知識や、みことばを覚えているだけでなくて、洗礼を受けて教会に通っているだけでな.くて、毎日の生活のなかで、神のみことばを行うことが必要です。うまくいってもうまくいかなくてもいいんです。やってみることが大事なんです。先ほども読みましたけれども、マタイの7章24節でイエス様は仰いました。
マタ 7:24 だから、わたしのこれらのことばを聞いてそれを行う者はみな、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。
うまくいくかどうか、ではなくて、うまく行かなかったらどうしよう、ではなくて、うまくいかなくても神のみことばを、毎日の生活の中でやってみる必要があります。そのことを通して、私たちは神に愛されていることが分かるようになります。
さて、このバラクの事件はここで終わっていません。敵の将軍シセラを倒したのは、バラクでもなく、デボラでもありません。もう一人の女性、ケニ人ヘベルの妻ヤエルです。突然ここにヤエルが登場します。ケニ人ヤエルは、イスラエル人ではないのに、主に忠実な人でした。ケニというのは「鍛冶屋」という意味であります。鍛冶屋を職業としていたんでしょう。そのためか、ヤエルは鉄のくいと槌を用いています。普通の女性が、鉄のくいと槌を武器に使うのは、相当慣れていないとできないはずです。
ケニ人は一般に、南パレスチナからシナイ半島にかけて住んでいましたけれども、このヤエルの家族は、士師記の4章11節にありますように、「ケニ人ヘベルは、モーセの義兄弟ホバブの子孫のカインから離れて、ケデシュの近くのツァアナニムの樫の木のそばで天幕を張っていた。」と書いてあります。多分、タボル山の近くに住んでいたと思われます。今回の戦場の近くですね。おそらく、鉄の武器や農機具を作って商売していた人達だと思われます。
4章の17節では、「シセラは徒歩でケニ人ヘベルの妻ヤエルの天幕に逃げて来た。ハツォルの王ヤビンとケニ人ヘベルの家とは親しかったからである。」とあります。シセラはヘベルたちがそこに住んでいたのを知っていたんですね。
ハツォルの王ヤビンとヘベルの家は親しかった、と書いてあります。このシセラとケニ人ヘベルの関係は、おそらく、先ほどお話ししましたように、シセラの九百両の鉄の戦車の製造や修理を、ヘベルが請け負ったいたからではないでしょうか。そういう関係から、シセラは安心して、ヤエルの天幕に逃げ込んだものと思われます。
しかし、主はここに一人の賢い神のしもべを持っていました。ヤエルは最高の親切ともてなしを持って、神に敵対する者に安心と油断を与え、神に敵対するものを撲滅してしまっております。
私たちがこの世の人々に対して、キリストを証しする武器はなんでしょうか。
それは神の愛を行うことです。神の愛が人々の心に刺さることによって、神に反逆する性質は死滅します。
使徒の働き2章37節で、「人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロとほかの使徒たちに、『兄弟たち。私たちはどうしたらよいでしょうか』と言った。」とあります。神の愛による働きは人々の心に刺さる、と書いてあります。
バラクがシセラを追って、ヤエルのところまで来た時、戦いは女の人の勇敢な信仰によって、もう終わっていました。一体バラクは何をしたんでしょうか。彼が恐れていたことは起きたんでしょうか。確かに、神様が教えた通り、一万人を集めて、姿を見せただけです。
ここで、私たちが悟るべきことは、何でしょうか。
私たちは、知識があっても、儀式を守っていても、議論で勝っていても、みことばを信じていなければ、堕落してしまうことであります。困難や課題ばかりに捕らわれていると、たましいは滅んでしまいます。神のみことばを食べていないと、力を失います。
敵の大軍を見ると、誰でも足がすくむでしょう。しかし、女預言者デボラは、主のみことばをバラクが行うまで語り続けました。バラクはなかなか腰をあげなかったけれども、腰を上げるまで、みことばを教え続けました。
神様はバラクが知らないところで、神の器ヤエルを備えておられました。結局、神が戦って下さり、バラクは戦いませんでした。敵の軍隊を追いかけただけであります。彼が恐れたことは、何も起きなかったのです。
私たちは、毎日の生活の中で、小さなことでもみことばを信じて活用することを身につけさせていただきたいと思います。そうすることによって、私たちは、神の栄光を拝することができるようになります。
バラクは、信仰の勇者の中には入れないかもしれないけれども、しかし、助けられることによって、神の栄光を現わすことができる、そういう器に用いられることが大事です。
私たちも、日頃の生活の中で、もう一度、神様の戦いを表すみことばの信仰を用いさせていただきたいと思います。
お祈り
恵みの深い天のお父様、こうして私たちの日ごとの生活の中にも、信仰の弱い者を強くしてくださって、神のみことばを信じて従っていくとき、イエス様は姿を現す、と仰いました。
私たちもこの世の人々の前に姿を現して生活しております。
「戦え」、とは仰いませんでしたけれども、みことばを信じて従っていく時、神様は必要な時に、必要な助け人を起こして、神の勝利、栄光を現わしてくださることを見させてくださいました。
そして、私たちの生涯についてもそうであります。困難な戦いや、敵の大軍を見ると、後ろに下がってしまうような恐れを感じることが少なくないですけれども、それでも神様は私たちを導いてくださり、「信じるなら神の栄光を見る」と教えてくださいました。
どうか、神様の栄光が現されるように、今週も信仰の生活ができますように助けてください。神の愛の働きを通して、神の愛のみことばがこころに刺さるように、導いてください。
尊いキリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。
地の塩港南キリスト教会牧師
眞部 明

ナザレの町はずれにある「突き落としの崖」から臨むタボル山。士師記の時代に、バラクの軍勢が士師デボラと共に陣取ったところです。
<今週の活用聖句>
箴言3章5節
「心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りにたよるな。」
信仰の列伝の目次
地の塩港南キリスト教会
横浜市港南区上永谷5-22-2 TEL/FAX 045(844)8421