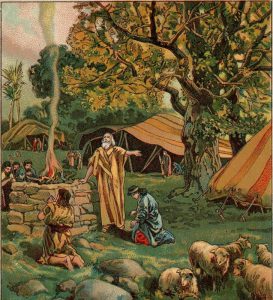音声:信仰の列伝(12) アブラハムの信仰(2)「出発の信仰(2)」

ハンガリーの画家 József Molnár (1821 – 1899) による「Abraham’s Journey from Ur to Canaan(ウルからカナンへのアブラハムの旅)」(Hungarian National Gallery蔵、Wikimedia Commonsより)
2016年10月16日 (日) 午前10時半
礼拝メッセージ 眞部 明牧師
へブル人への手紙11章8節
11:8 信仰によって、アブラハムは、相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで、出て行きました。
はじめの祈り
「信仰によって、アブラハムは、相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで、出て行きました。」
恵みの深い天のお父様、こうして一週間の旅路を、いろいろな困難な課題を乗り越えさせていただいて、主を礼拝して、新しい週を迎えることを感謝いたします。
今週も私たちは、未知の週に足を踏み出すことであります。
いろいろな困難が待ち受けていると思いますけれども、私たちが目指しているところを、しっかりと心に留めて歩ませてくださり、信仰によって勝ち取っていけますように。
主がともにいてくださることを心から感謝いたします。
みことばを祝してください。
尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今回も、アブラハムの信仰の続き、出発の信仰(2)をお話しします。
創世記の12章4節を見ますと「アブラムは主がお告げになったとおりに出かけた。ロトも彼といっしょに出かけた。アブラムがハランを出たときは、七十五歳であった。」と書いてあります。当時でも、75歳の年齢は、新しい人生に挑戦する年齢とは思われていなかったようであります。ここから、まったく新しい課題を持った人生をスタートするということは、当時としても考えられていなかったようです。
しかし、アブラハムの場合は、信仰の挑戦は、中断されていた信仰の旅、カラン(またはハラン)までは来ておりましたけれども、そこからふたたび再出発することです。それに立ち向かうのは年齢ではありませんでした。モーセは80歳から、イスラエルの民をシナイの荒野の旅の指導に立ち向かっております。
今、人生100歳を迎える人が非常に多くなっていますけれども、それでも、75歳、80歳になりますと、高齢と言われています。人が、神のお仕事にたずさわろうとすると、年齢制限をかけようとしやすい。もう年をとっているから何もできない、と思いやすいことですけれども、神の召しに従うのに必要なのは、年齢ではなくて信仰であることを教えられます。
私たちは、「何ができるか」よりも、神様を信じていることの方が、とても大事であります。年を取ると、できなくなることが増えますけれども、そのことで失望する人が多くありますが、そのことより大切なことは、イエス様を信じていることであります。
なんと言っても大事なことは、アブラハムが神様のお声を聞いた時に、すぐに従ったことであります。彼はいつも、従うことを、遅らせませんでした。神に従うことを、後回しにしなかった。これは私たちに、とても大切なことを教えていると思います。
神様が「モリヤの山で、イサクを全焼のいけにえにささげよ。」と命じられた時も同じです。アブラハムは、即刻、服従しました。
創世記22章3節を読んでみたいと思います。
「翌朝早く、アブラハムはろばに鞍をつけ、ふたりの若い者と息子イサクとをいっしょに連れて行った。彼は全焼のいけにえのためのたきぎを割った。こうして彼は、神がお告げになった場所へ出かけて行った。」
「翌朝早く」であります。昼頃でもなく、夕方でもありません。
彼はいろんなことを自分で考えていない、ということですね。神様のみ声が真実、本当であることが分かったら、すぐ翌朝、出発した。
アブラハムの信仰の特徴は、いろいろありますが、その一つは、主の御命令にすぐ従うことでした。
このことが、アブラハムが祝福を受けた第一の重要な理由であります。
人間によけいなことを考える時間を与えると、自分の知恵で、信仰を遅らせてしまいます。ですから私たちは、日頃、神様から示されることがあれば、後回しにしないで、まず第一にそのことに心を用いて、取り組ませていただければ幸いと、思います。
そういう心の姿勢が、祝福の道へと繋がっていく。そのことをアブラハムは、私たちに示してくれています。
彼は、主に従うことを、遅れさせなかったし、躊躇しなかった。この「すぐに従う」態度こそ、神様が喜ばれることです。神様が「これをしてください」と言った時に、すぐに従う時、神様は喜ばれます。
み言葉と聖霊によって、神のみ声を聞いたならば、その時、行く先が、自分の目にはどんなに困難に見えても、神様が語られた時が最もよい機会だということを、悟っていただきたいと思います。
私の生涯を振り返ってみましても、私の経験でそれが分かります。私が主に従うことで、主を求める人が起こされました。少ない人数でありますけれども、幸いなことであります。
もし私たちが、主に従わなかったなら、従うことに躊躇していたならば、私たちは今の恵みを受けていなかったでしょう。
私の証しや、皆さんの証しを通さなかったら、ご家族や友人たちはイエス様の福音を聞く機会がなかったでしょう。神様の光を受ける機会がなかったでしょう。よき交わりの時がなかったでしょう。
私は何冊かの本を出していますけれども、一番最初の本「知られざる力」を出版しようとしていた時に、お金が全くありませんでした。
ところが、一人の姉妹から、「出版のために」というメモと一緒に、五千円の献金が届きました。その時私は、「これは、主が出ていけ」と言ってくださったと信じて、最初、確か五百冊作ったと思います。それを知人に送ったり、キリスト教書店にお願いして、「来られた方に差し上げてください」と頼みました。すると、「友人にもあげたいので」と言って、何冊も求めてくださる方がいて、御献金下さり、増刷の費用が与えられました。こうして文書伝道が始まったわけであります。
1978年4月、私は、それまでは九州の大分市で奉仕をしていましたけれども、そこから横浜のこの地に来て、地の塩教会を始めました。その時も、何の保証もなくお金もありませんでした。ただ主の導きだけであります。
ある日の責任役員会の前に、不動産屋さんの前を通った時、この場所の建物が売りに出ていました。その日の責任役員会で、この場所を、地の塩教会、として購入することが決まりました。
全然予定していないことでありましたけれども、主の指示に躊躇していれば、今もなお、借家で伝道していたことでしょう。一冊の本も出せなかったと思います。
「従うこと」は、非常に重要であります。問題や課題を、乗り越えなくてはなりませんけれども、神様が示してくださることは躊躇なく従うことが大事だということを、学びました。
アブラハムは75歳から従い、モーセは80歳から主の使命を担って、新しい神の道を歩み始めております。
私も25歳でイエス様を信じて、今年で74歳になりました。身体もだいぶ衰えてきましたけれども、主の召しと導きには、躊躇してはならないということを、教えられました。
誰でもその生涯は、その途中で終わると思いますけれども、私も例外ではないと思いますが、この神様のお仕事は、私の仕事ではなくて、主の働きですから、主が成し遂げてくださいます。下手に人間の知恵を使って、ことを運ばない方がいいと思います。
第二歴代誌20章15節後半に、「この戦いはあなたがたの戦いではなく、神の戦いであるから。」と書いてあります。
同じ第二歴代誌20章17節でも、「この戦いではあなたがたが戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなたがたとともにいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ。恐れてはならない。気落ちしてはならない。あす、彼らに向かって出陣せよ。主はあなたがたとともにいる。』」と言われているんです。
とかく私たちは、いろいろな戦いをする時、困難を乗り越えて働く時に、一生懸命に自分が背負わなければならないと思って苦労してしまいますけれども、これらのみことばを見ると「この戦いではあなたがたが戦うのではない」と言っております。「主の救いを見よ。恐れてはならない。気落ちしてはならない。主はあなたとともにいる」と仰いました。
主のご計画の働きが進んでいく限り、働き人は変わると思います。確かに私がイエス様を信じたころと、今とでは、働き人がどんどん変わっています。団体や組織も変っています。しかし、聖書の真理と聖霊のみわざは続いております。
主は、迫害者サウロを捕らえて、ご自身の使徒とされました。主は必ず、ご自身に相応しい器を備えて、いつでも御国の建設を続けておられます。主の働きだからですね。
いつでも新しい出発をする時には、困難や悪条件がたくさん見えてくるわけです。
私たちはそれを見て、信仰が躊躇しやすいものであります。足が引っ張られてしまいます。目の前にいろいろな難しい問題や課題が、見えてくるわけです。現れてきます。アブラハムも同じでありました。
いかにして、信仰でよじ登っていくのか。私たちは、次のことを、はっきりと確認しておきたいと思います。
それは、神に従う時は、神のみ声を聞いたその時であります。その時、なんでもかんでも従うのではなくて、主の声が神の御声であるかどうか、十分に確かめる必要があります。
第二コリントの11章13節~15節を読んでみたいと思います。
11:13 こういう者たちは、にせ使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。 11:14 しかし、驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。
11:15 ですから、サタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても、格別なことはありません。彼らの最後はそのしわざにふさわしいものとなります。
神の義のしもべに変装している偽者、サタンの手下どもがたくさんいる、ということです。大方の人が、これらの人に惑わされてしまっているんですね。自分たちが、惑わされていることに気づかない。クリスチャンはそうであってはなりません。
テトスの1章10節、11節を読んでみましょう。
1:10 実は、反抗的な者、空論に走る者、人を惑わす者が多くいます。特に、割礼を受けた人々がそうです。
1:11 彼らの口を封じなければいけません。彼らは、不正な利を得るために、教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。
特に割礼を受けた人々がそうです、と言っています。ユダヤ主義の割礼主義者のことを言っています。ユダヤ教の人ですね。伝統に凝り固まっている。儀式に凝り固まっている。戒めに凝り固まっている。
自分たちが伝統的な、中心的な集団だということを、強調しているようでありますけれども、教えてはいけないことを教えている。これは非常に危険なことですね。
福音を語る教会として、そう看板をあげていて、教えてはいけないことを教えている。
こういうことがはびこってくる時代が来ると、パウロは言っています。
もう一つ、第二ペテロの3章16節、17節を読んでみましょう。聖書を曲解している、滅びを招いている人のことが書いてある。
3:16 その中で、ほかのすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な、心の定まらない人たちは、聖書の他の個所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いています。
3:17 愛する人たち。そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいて、よく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。
迷いに誘い込まれないように、自分自身の信仰の堅実さを失わないように、と言っています。信仰の堅実さを失うことは、非常に危険なことであります。聖書のことばを、自分の都合の良いように捻じ曲げてはいけないですね。
ヨハネも警告しました。第一ヨハネ4章1節
4:1 愛する者たち。霊だからといって、みな信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを、ためしなさい。なぜなら、にせ預言者がたくさん世に出て来たからです。
聖書はあくまでも、健全な真理を追い求めるように命じています。堅実さを失わないように。どんなに素晴らしいお話でも、その生活が堅実さを失っていくようであれば、そこから離れるようにしなければなりませんね。
次に、ヘブル11章8節の第二のテーマに入ります。
創世記12章1節では、ただ、「わたしが示す地へ行きなさい。」とだけ、アブラムに告げられました。
ところがヘブルの11章8節では、「相続財産として受け取るべき地に出ていけとの召しを受けた」と言っています。もっと詳しくなっていますね。
アブラムは、自分が向かう地は、神が相続財産として与えてくださる地であることは、確信できましたが、それが、どこで、どんなところであるかは、まったく知らされていません。それはちょうど、私たちが天の故郷、神の都を目指しているのと同じです。その点の故郷、神の都が、どんなに素晴らしいか、素晴らしいとは聞いてはいるけど、具体的にはよく知りません。
なぜ主はアブラハムに、その地がカナンの地であることを知らせなかったのでしょうか。もちろんカナンの地が、最終地ではありませんけれども。
それは、もし、アブラハムが行くべき地がカナンであることを知って旅するなら、もはやアブラハムには、信仰が必要なくなってしまうからです。行く先が分かって、それがどこにあるか、あと何日くらいしたら着くのかが分かったら、もう信仰が必要なくなってしまいます。
神様は、私たちが一歩一歩神に従うことによって、進んで行くことを望んでおられます。毎日毎日、主に助けを求め、信仰によって主を求めながら歩んでいくことが、大事なことであります。私たちは、明日どんな日が来るかを知ることよりも、知らなくても一歩一歩あゆんでいくことが必要であります。主がアブラハムに求められたことは、カナンの地に早く着くこと、無事につくことではなくて、その地が分からなくても、一歩一歩、神に従うことでありました。
アブラムは、どこに行くかよりも、何日かかって行くかよりも、主とともに歩み、主に従うことを、心からの喜びとして歩んでいたんです。信仰によって歩むことが大事だったんですね。途中、厳しい試練や困難がありましたけれども、めげずに従い通しました。
私たちにとって一番大事なことは、一歩一歩、主に従うことであります。
ローマ8章18節をお読みしたいと思います。
8:18 今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。
アブラハムは、一回だけの召しの声に従ったのではなくて、毎日、いつも主の御声を聞きつつ歩んでいた。毎日、みことばの光の照らす道を歩んだのです。そして記念の場所では、感謝の祭壇を築いて、主の御名を呼んで礼拝しました。
私たちは、毎週礼拝を捧げているわけですけれども、それは日曜日だから礼拝している、というだけではなくて、一週間の感謝の祭壇を築いて礼拝をささげているわけであります。
私も毎日、神様が光の中におられるように、私も光の中を歩み、そしておりあるごとに、感謝の記念の祭壇を築き、主と親しく交わる礼拝を捧げたいと思います。
マタイの18章20節に有名なことばがあります。
18:20 ふたりでも三人でも、わたしの名において集まる所には、わたしもその中にいるからです。」
キリストの名前が付いている教会に集まっていればいい、というわけではありません。心にイエス様を持っている人が集まる所が教会です。ですから私たちも、こういう礼拝を絶えずささげたいと思います。ただ教会に行っているというだけではなくて、アブラハムのように天の故郷を目指している、そういう礼拝をささげたいと思います。
そういう信仰の旅は、地上の幸福や繁栄よりも、天の故郷がはかりしれないほど勝っていることを悟り、確信した人だけができます。しかし私たちは、神と共に歩んでいても、とかく自分の期待通りに導いてくださることを、求めがちです。
アブラハムも、世継ぎの誕生を約束されましたが、期待通りに生まれてきてくれませんでした。実は、父なる神様は、アブラハムとサラに、その力が全くなくなるのを待っておられたのです。アブラムとサラは、自分たちには可能性がないと考えると、エジプトの女奴隷ハガルからイシュマエルを生んでしまいました。期待通りにいかなかったからです。
しかし、天が地よりも高いように、主の御心は私の考えよりはるかに高いのです。それゆえ、私の考えを捨てさせられます。
また主は、ひとり子イサクを与えられたのに、ご自身がお与えになったそのイサクを、モリヤの山で全焼のいけにえにするように命じられました。とんでもないご命令であります。あり得ないことです。アブラハムには、神様が与えてくださった世継ぎのイサクを全焼のいけにえにするなんて、矛盾しております。理解できない、決して受け入れられない、無理なご命令であります。アブラムがどんなに知恵を絞って考えても、受け入れられることではありません。こうして主は、徹底的にアブラハムの信仰と愛を試みられたのです。
まさにこれは、人間が通ったことのない道です。私たちの信仰の導き手は、人が通った同じ道を二度と通ることはありません。神様はいつも、未知の道を導かれています。
カデシュ・バルネア以後、主の導きがなくなって、人間の知恵でシナイの荒野を旅した時、イスラエルの民は40年以上もさまよい続けました。主が導かれなくなると、人間はさまよった人生を歩んでしまうのです。
主が導かれると、紅海は分かれて、ヨルダン川の水も分かれて、渡っています。主が導かれる時だけ、私たちは天の御国を目指して歩んでおります。
聖書は、アブラハムが「どこに行くのか知らないで、出て行きました」と、記しています。信仰の歩みは、見えるところによらない歩みであります。
昔、海の航海技術を持たなかった船の船長は、パウロの時代もそうでしたが、陸が見える岸づたいに、島づたいに、航路を取りました。しかしやがて、航海技術が発達してくると、岸辺や島が見えなくても、太陽や星座の位置から計算して自分の位置を知り、航海をしました。
最近では、人口衛星のGPSとか位置情報から、昼でも夜でも嵐の日でも正確に自分の位置を知ることができて、安全に航海ができます。つまり、周りに何も見えていなくても、上からの電波によって正確に進むことができるわけです。今日、これは当たり前のことになっています。
アブラハムも同じ道を歩むことができませんでした。神様の導きを受けることが必要でした。
ヤコブの1章17節を読んでみたいと思います。良い賜物は、上からしか来ない、と言っています。
ヤコブ1:17 すべての良い贈り物、また、すべての完全な賜物は上から来るのであって、光を造られた父から下るのです。父には移り変わりや、移り行く影はありません。
私たちは、絶えず上からの光を求める必要があります。それにタッチするのは信仰ですね。アブラムはこのことを試みられています。自分の知恵では、目が曇ってしまう。
私が、あの金持ちの青年のように、多くの財産があり、体が健康で、人々の評価も高い、そういう状況の下でなら、イエス様から永遠のいのちをもらって、イエス様と共に歩んでもいい、と思っているなら、それは信仰ではありません。自分を、富と健康とこの世の安全と思われるもので囲っておいて、いくら信仰論を白熱させて議論しても、それが正論であっても、信仰ではありません。ただの自慢話になってしまいます。
本当に自分の生涯を捧げているものが、神様ではなくて、この地上のものであれば、どのような神学論を話しても、信仰ではありません。
主イエス様が、マタイ19章の金持ちの青年を受け入れられなかったのは、彼が求めていたものが間違っていたからではありません。彼が求めていたのは永遠のいのちです。しかし、目に見える自分の富に心が奪われ、本当に頼りにしていたのはイエス様ではなくて、自分の財産だったからです。こころに主の愛を求めていなかったからであります。それをイエス様は見抜かれました。ですから私たちも、このことを避けなければなりません。
信仰の旅路というのは、どこまでも真っすぐに伸びた一本道には見えません。北海道の道は、真っすぐに荒野を突っ切っているような道がありますけれども、信仰の道は、そういう一本道には見えていません。その逆で、むしろ、一歩先は暗闇に包まれていたり、雲や霧に覆われていたりして、はっきり見えてきません。
ただ、一歩進むと、次の一歩が現れてくる。そういうふうになっております。ですから、その道には突然、熊が現れたり、危険なわざわいが飛び出してくるかもしれません。ですから、怖がるわけです。それで恐れて躊躇してしまいます。
弟子たちは、嵐のガリラヤ湖を歩いてこられたイエス様を見て、「幽霊だ」といって恐れています。しかしイエス様は、「わたしだ。恐れることはない。信仰の薄い人達だな。」と言われました。みことばと聖霊を握って、しっかりと支えられていないと、先が見えていない旅路を歩むときに、不安と怖れにとらわれてしまいます。そして信仰の道を歩まなくなってしまう。この世の富や財産に、頼るようになってしまう。あの金持ちの青年と同じ道を、歩んでしまいます。そういう危険があります。
アブラハムは祝福を受けながらも、これらの点を徹底的に試みられました。信仰の父と呼ばれ、多くの国民の父となるために、神の国を相続するために、徹底的に試みられています。主はアブラハムにイサクを与えました。その大事なイサクを、全焼のいけにえにささげる様に命じております。そしてまた、イサクを戻されました。
人間的に考えると、なんと面倒なことを行なっておられるんでしょうか。このことを通して、アブラハムは、復活の信仰が与えられたんです。このことを通して、アブラハムの信仰は、また一段と強くなりました。変貌させられております。
ヘブル11章19節を読んでみましょう。そこにそのことが書いてあります。アブラハムはそれまでになかった信仰経験をしています。
ヘブル11:19 彼は、神には人を死者の中からよみがえらせることもできる、と考えました。それで彼は、死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。
復活の信仰は、新約になって与えられただけではありません。アブラハムはイサクを捧げることによって、復活の信仰を持ちました。「これは型です」と書いてありますから、信仰の型であります。
しばしば、私の先行きには、不確かに見えたり、暗闇に入っていくような感じがします。しかし、私を導いてくださる神様は、私にとって最善のことしかなさらないお方であることを信じて、今日も明日も、進ませていただきたい。
アブラハムは、カルデヤのウルから、一歩一歩、主に従って歩むことによって信仰と希望と愛を、成熟させてきたわけです。希望というのは、復活の希望であります。
主は、ペテロが水の中に沈みかけた時も、引き揚げてくださいました。
主を3回「知らない」と言って否定した時も、主は「あなたはわたしを愛しますか」と尋ねてくださいました。
取税人ザアカイもお救い下さり、迫害者サウロもお救い下さり、主のしもべとしてお用いくださいました。
主は、主を信じて従う弱い者、助けなき者を助けてくださいます。主に従う機会は、躊躇し熟慮しているうちに、失われてしまいます。まず今日、今、従うべきことを、従いたいと思います。
大きなことに取り組む前に、信仰の歩みも先ほどお話ししましたが、いつでも先がはっきり見えない面があります。しかし、今、神と共に歩むことによって、勝利の確信をつかむことが求められています。神の全能の力は、大きなことをやり遂げることによってではなくて、目の前の小さなことに従うことを通して、私たちは神の全能の力を体験していきます。
ところが私は、神と共に歩む確信よりも、先の結果を見て安心しようとしがちであります。これは信仰の態度ではありません。見えるところによって、歩みやすいんです。
イエス様はトマスに、「見ずに信じる者は幸いです」と仰いました。
アブラハムは、ただ、自分とともに歩んでくださるお方に従っているだけで、満足でした。このことはすべての人に必要です。
私は、主とともに一歩一歩あるくだけでは満足せず、できるだけ先の方まで知りたいと詮索したり、推測したりします。それで先はどうなるのかと推測しながら、歩もうとしやすいんです。
信仰者にとっては、みことばは足のともしび、道の光、主と共に、一歩一歩あるくことが、最も重要な訓練であります。これができることが、成熟した信仰者の状態です。エノクもノアも、これができる人でありました。
私の信仰の失敗の原因は、主の導きの先回りをして、次の曲がり角の先はどうなっているかを、先回りして早く見たいということから、起きているわけです。その先はどうなっているんだろうか、この山を越えたらどうなっているんだろうか、それを見たい、知りたいと思いやすいことです。
主が私に与えてくださったことは、「足のともしび、道の光」であって、これは一歩先を照らすことであります。遠くまで照らしておりません。明日のことも、三日先のことも、一週間先のことも照らしていません。信仰の歩みには、それが一番適切だからです。足のともしびで、遠くまで照らそうとすると、何も見えなくなってしまいます。そういうことを、私たちは願いやすいわけです。
私たちは旅行する時、すでにそこには道があり、ホテルがあり、ということを想像します。航空券や列車の切符を予約します。アブラハムが旅したころは、ほとんどが砂漠と荒野で、新幹線もなければ、飛行機もない。道があっても、ほとんどが荒地であります。舗装された道があるわけではありません。道なき道を歩んで行く。
私たちが歩む信仰の道も、みんなが営んでいる生活の続きのように見えるかもしれませんが、誰でもすべての人が、誰も歩んだことのない明日を迎えているのです。神様は、私を歩ませるために、荒野に道を設け、海の底や川の底に道を開いてくださいます。
主は毎日、誰も通ったことのない道を、導いてくださっているのです。ですから誰でも、主の導きがなかったら、道に迷ってしまいます。大事なことは、主とともに、一歩一歩、歩むことだけです。これは誰にでもできます。そうすることによって、主と親しく交わり、平安や安心を経験し、主に信頼することを実際に経験します
自分の知恵で、自分の歩み方をしようとすると、こうでもないか、ああでもないかと心配して、道に迷ってしまいます。決して、主とともに歩む道を見つけることができません。
アブラハムはどこに行くのか分からなかったけれども、それを自分の知恵で詮索しなかった、探さなかったんです。もし自分の知恵で探していれば、彼は、神に従うことができなくなっていたでしょう。アブラハムは「信仰とは、そういうことを一切詮索しないで、歩むことなんだ」ということを悟っていたのです。
ただ彼は、主が導かれる地は、主が相続財産として与えてくださる地であることを確信して、従っていました。彼は、行くところが、神様が与えてくださる地であることを確信することで、十分満足していました。
ここでもう一つ、注意すべきことがあります。
主は、アブラハムに相続財産として、カナンの地を備えておりましたが、その地を実際にアブラハムのものにするには、アブラハムが信仰によってその地に到着して、受け取らなければなりません。受け取らないと、その地は他の人の手に渡ってしまいます。
この原理は、私たちの生活にも当てはめられます。アブラハムは、目に見えない、具体的には何もわかっていない、しかし確かな相続財産の地に向かって行ったのです。彼はその確実さを、どのようにして知ったのか。それは日々に、一歩一歩、主とともに歩む生活をすることによってです。私たちは、信仰によって歩むことを通さないと、神の相続財産を受けることができません。
次に、第三の点、「どのように従ったのか」というお話をします。
ヘブルの11章8節では、「これに従い」とだけ記しています。
創世記12章5節には、アブラムと一緒に出発した人の名が記されています。まず、妻のサライ、そして甥のロトです。
ロトは、彼自身、信仰がはっきりしない人ですが、おじさんのアブラムはいつも祝福を受けていることを目ざとく見抜いて、アブラムと行動を共にすることを選びました。ロトは、損得を計算して、アブラムに従った人でした。
しかし、アブラムの兄弟ナホルは、アブラムと一緒に行きませんでした。父テラの墓のあるパダン・アラムにとどまっております。それゆえ、出発するにしろ、留まるにしろ、それぞれの人に動機があり、目的があり、決断があったことが分かります。その中で、アブラムだけが明確に主の召しを受けて、それに従っていることが記されています。
創世記12章4節で、「アブラムは主がお告げになったとおりに出かけた」とあります。
アブラムの出発は、主の召しに対する従順な服従であったことを記しています。アブラムは、どこに行くのか詮索せず、躊躇や抵抗もせず、しぶしぶ従ったのではなく、主に信頼して、主に従いました。主とともに歩むことを喜びとして選んだのです。このような従順な服従は、主を喜ばせます。
さんざん自己主張して抵抗し、泣きわめいて、エジプトに帰りたいとわめいた、モーセの時代のカデシュ・バルネアのイスラエル人のように、そのあとになって従っても、もはや主はともに行ってくださいません。同じ旅路をしているようですけれども、主とともに歩んでいる生活と、その後のさまよう放浪の旅とは、まったく別であります。不信仰になれば、もはや主はともにいてくれません。自発的に、喜んで、信頼して主に従う信仰を、神様は祝福してくださいます。
ヘブルの11章8節から、アブラハムの出発の信仰を、三つの面からお話ししましたが、ここで簡単に申し上げますと、
第1、いつ従ったのか。
神の召しを受けて、その時、「すぐ」でした。毎日、主の御声を聞いて「すぐに従う」ことを、心得ましょう。そうすれば、主はお喜びくださいます。後回しにしないようさせていただきましょう。
第2、どこに向かって進んでいったか。
具体的には、何もわかっていない所、実際には何も結果が見えていない所です。しかし、そこが神の相続財産の地であることを確信して歩みました。この確信は、神とともに歩む経験を通して確認したんです。私たちの信仰の確信は、日ごとの神との歩みですね。将来が全く見えていなくても、必ず、神の相続財産を確信できるようになります。大事なことは、主と一歩一歩、歩むことであります。そのことを、心に留めさせていただきましょう。
第3、どのように従ったか。
あれこれ心配せずに、まったく信頼して、従順に主とともに歩みました。これこそが、創世記17章1節後半の「わたしは全能の神である。あなたはわたしの前をあゆみ、全きものであれ。」という、みことばの実現でありました。これに従ったから、神様はアブラハムを愛されて、祝福されました。私たちも、このアブラハムの信仰を受け継がせていただきたいと思います。そして、私たちの相続財産を受け継がせていただきたいと思います。
これからも、アブラハムの話を続けていくわけですけれども、信仰で一番大事なことは、先がどうなるかを見えていることではなくて、一日一日、一歩一歩、主とともに歩むことの大切さを、心に留めていただければ幸いです。そして、主とともに歩む生活を確立させていただきたいと思います。
お祈り
「信仰によって、アブラハムは、相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで、出て行きました。」
恵みの深い天のお父様、今週の旅路もあなたが導いてください。
毎日、私とともに主が共にしてくださることを確信して、みことばがいのちの光となり、足の灯となって、一歩一歩の歩みを主が喜んでくださることを、私たちは体験しながら、しかし、私たちには、相続財産が備えられて、そこに向かってまっすぐに、主が連れて行ってくださることを確信して、歩ませてください。
尊いキリストの御名によって、お祈りいたします。
アーメン。
地の塩港南キリスト教会牧師
眞部 明
<今週の活用聖句>
コリント人への手紙第二、4章18節
「私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。」
地の塩港南キリスト教会
横浜市港南区上永谷5-22-2 TEL/FAX 045(844)8421